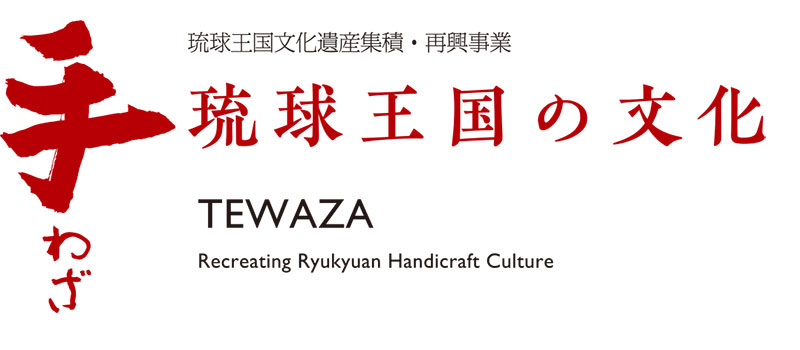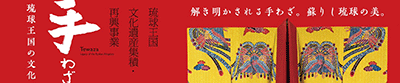会期:
令和3年10月19日(火)~12月12日(日)
展示場所:
文化交流展示室 第9・10・11室
概要:
沖縄県は、かつて琉球王国として独自の文化を繁栄させていました。亜熱帯気候を活かし、煌びやかな漆器や、色鮮やかな染織品が王府の管理下で製作されました。また国内は、海洋交易によりもたらされた諸国の宝物で満ちていたと伝えられます。しかし、近代化の波や第二次世界大戦中の激しい地上戦により、当時の有形無形の文化遺産の多くが失われてしまいました。同時に、代々大切に受け継がれてきた琉球の心や技術などの手わざも途絶えることになりました。
琉球王国の美しい文化財を現代によみがえらせるため、職人と研究者が協力して8分野(絵画、木彫、石彫、漆芸、染織、陶芸、金工、三線)にわたる失われた手わざの解明に挑みました。模造復元の過程は非常に困難でしたが、職人と研究者が協力して乗り越えた結果、様々な発見が得られました。
本展では、それら模造復元品を中心に展示し、その製作工程をご紹介します。現代によみがえった文化財をご覧いただくとともに、琉球王国の美を感じていただければ幸いです。
出品リスト :
*本展では、現代に製作された作品を主に展示します。(琉球王国時代の作品も展示します。)
*一部作品を展示替えします。
模造復元とは
原資料について調査・研究を重ね、製作された当時の姿を忠実に復元し、新たに製作することを指します。可能な限り製作当時と同じ材料と技術を使って製作される模造復元品は、21世紀の文化財です。



琉球王国文化遺産集積・再興事業について、詳しくは 沖縄県立博物館・美術館の特設サイト をご覧ください。
手わざの秘密を探る
めざましく発展した科学技術により、文化財についてより多くのことがわかるようになりました。しかしそれらがどのように作られたのか…すなわち「手わざ」については、未だよくわからないことが多くあります。
「手わざ」をもっともよく知る方法は、実際に作ってみることです。同じ作品を作るためには、同じ製作工程で作る必要があり、その手順を明らかにすることは材料や手わざの秘密を解き明かす糸口になります。今回の模造復元の過程で復元に携わった人々には、先人の手わざの知恵と心に触れる追体験の学びがありました。
模造復元品を製作する過程で解き明かされた数々の手わざの秘密を覗いてみてください。
中国絵画を手本とした琉球の絵師たち

四季翎毛花卉図巻
令和元年度復元(原資料 康煕51年〔1712〕)
中国人絵師・孫億による7メートルにも及ぶ絵画を模造復元しました。代表的琉球絵師の山口(神谷)宗季が模写したと伝えられ、繊細な描線と写実的な表現が特徴です。今回は、九博所蔵の原資料と並べて展示します!
油と水を利用した絵付

赤絵枝梅竹文碗
平成30年度復元(原資料19世紀)
中国から伝来した絵付けの技法が使われています。原資料も同時に展示!
刺繍に秘められた多様な技法

伊平屋阿母加那志の繍衣裳
令和元年度復元(原資料15-16世紀)
完全に途絶えた琉球独自の刺繍、琉球古刺繍を復元しました。
細やかな彫金は必見!

聞得大君御殿雲龍黄金簪
平成28年度復元(原資料16世紀)
最高位の神職に就いた女性、聞得大君が使った簪です。重そうに見えますが中はドーム状の空洞になっています。
線刻と金箔による豪華な沈金

朱漆巴紋沈金御供飯
平成30年度復元(原資料17-18世紀〔原資料は亡失〕)
高さ60㎝!祭祀儀礼用の漆器です。プロジェクションマッピングで、手わざの工程をご紹介します。
琉球の特別な楽器

三線 志多伯開鐘
平成30年度復元(原資料19世紀)
当時の音色に近づくよう復元を試みました。開鐘とは、名器にのみ付けられる称号です。
沖縄戦で破壊された仁王像

円覚寺仁王像吽形
令和2年度復元
(原資料 15世紀末~16世紀初期)
円覚寺にあった仁王像。円覚寺は琉球王家の菩提寺です。樹種の分析などから、このお像は琉球王国ではなく、室町時代の日本で作られたことがわかりました。
糸から復元された高貴な織物

芭蕉桃色地経縞絽織衣裳
令和元年度復元(原資料19世紀)
糸芭蕉の糸で織られた王族の女性の衣裳。美しい艶の糸にも注目です。
圧倒!王家の紅型

黄色地鳳凰蝙蝠宝尽青海波立波文様
紅型袷衣裳(表)赤地平絹(裏)
令和元年度(原資料18-19世紀)
中国の皇帝から贈られる衣服の文様を模して染めた紅型。原資料は琉球国王の尚家に伝わった国宝です。
関連イベント
*開催状況に変更があった場合はホームページでお知らせします。
ワークショップ『琉球古刺繍をやってみよう』【要申込み・10名】
日時:
令和3年10月31日(日)13時30分~16時00分
講師:
寺田貴子 氏(活水女子大学 特別専任教授)
会場:
九州国立博物館 研修室
定員・参加費:
10名・無料(申込先着順)
申し込み方法:
展示解説・きゅーはく☆とっておき講座【先着144名】
日時:
令和3年11月14日(日)13時30分~15時00分
講師:
桑原有寿子(九州国立博物館 学芸員)
会場:
九州国立博物館1階ミュージアムホール
詳細は ミュージアムトークページ をご確認ください。
展示解説『8分野の手わざ解説』【先着144名】
日時:
令和3年11月20日(土)13時30分~15時00分
講師:
篠原あかね(沖縄県立博物館・美術館 学芸員)
会場:
九州国立博物館1階ミュージアムホール
製作者による報告会『手わざの秘密を探る』【先着144名】
日時:
令和3年11月21日(日)13時30分~15時30分
講師:
絵画:久下有貴 氏
木彫:岡田靖 氏(動画出演)、杉浦誠 氏
漆芸:前田貴子 氏、宇良英明 氏
会場:
九州国立博物館1階ミュージアムホール
定員・参加費:
144名・無料(先着順・申し込み不要)
講演会『琉球の染織と模造復元について』【先着144名】
日時:
令和3年12月12日(日)13時30分~15時00分
講師:
山田葉子 氏(那覇市歴史博物館 主任学芸員)
会場:
九州国立博物館1階ミュージアムホール
定員・参加費:
144名・無料(先着順・申し込み不要)