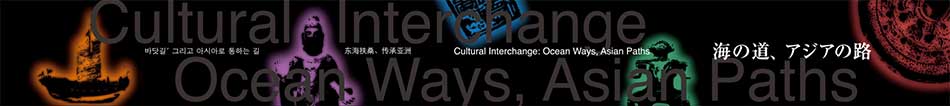
文化交流展示室では、日本とアジア、ヨーロッパとの文化交流の歴史を紹介しています。旧石器時代から江戸時代までを5テーマに分け、それぞれの文化交流を物語る作品を展示しています。見学の順序は自由!どうぞお好きな時代からご覧ください。さあ、出発しましょう!
文化交流シアターの愛称が「きゅーはくみるみる」に決定しました
開館20周年を記念し、(公財)九州国立博物館振興財団より贈呈された文化交流展示室の「文化交流シアター」の愛称が「きゅーはくみるみる」*に決定しました。
*『きゅーはくみるみる』
「映像を見る」ことに加え、「踏んでみる」、「触ってみる」、「やってみる」といった前向きにチャレンジする意味もあることから、この愛称が選ばれました。
歴史ドラマの中に埋没するような仮想空間やひとの動きに反応する映像空間をお楽しみください。
二つのコンテンツを交互に上映します(1時間に3回ずつ)。
太宰府タイムトリップ
大宰府政庁が置かれた奈良時代への時間の旅を通して、防衛拠点から政治・文化の発信地へと姿を変える太宰府が、現代につながっていくさまを体験できます。


キューハクふむふむ
文化交流展の5つの時代区分に応じたアニメーションを正面と左右の壁に投影。床に投影されたアイコンを踏むと、アイコンが壁へと動いて解説が始まる対話型コンテンツです。博物館の展示内容をモチーフに日本とアジアとの文化交流の歴史を遊び感覚で楽しめます。


展示室紹介
1 縄文人、海へ Jomon Culture: Ocean-Bound

3万5千年前~紀元前4世紀
氷河期であった旧石器時代。人々は大型動物を狩り、植物を採集し、遊動生活をおくっていた。縄文時代には気候が温暖化し、森にはたくさんの木の実がなり、小型動物が現れ、海は豊かな漁場となった。人々は土器を作って食料を煮炊きし、定住生活をおくり、飾り、祈り、弔いも行った。サケなどの食料が豊富な東日本では、特に文化が花開いた。
「1 縄文人、海へ」の展示作品
2 稲づくりから 国づくり Political Power: Cultivating Rice

紀元前4世紀 ~ 紀元後7世紀
弥生時代、大陸から米作りや金属器が九州に伝わった。農作業を共同で行なう中で人々をまとめる人が現れ、やがて地域を治める王になった。古墳時代には列島の大半を治める大王が現れた。大陸からは多くの人々が渡来し、乗馬の文化や須恵器製作の技術を伝えた。九州では石人や装飾壁画によって首長の死後の安寧を祈る独自の古墳文化が展開した。
「2 稲づくりから 国づくり」の展示作品
3 遣唐使の時代 Nation Building: The Age of the Envoys

7世紀 ~ 12世紀
奈良時代の日本は唐の都長安に遣唐使を送り、先進的な国家制度や仏教を学び、国際色豊かな品々を持ち帰った。大宰府はアジアとの外交・貿易の拠点として繫栄した。平安時代には、渡来の文化を基盤に、「仮名」に代表されるような日本独自の新しい文化が生まれた。仏教でも密教や極楽往生を願う信仰が流行し、未来に経典を残すために経塚が盛んに造られた。
「3 遣唐使の時代」の展示作品
4 アジアの海は日々これ交易 Merchants of the Asian Seas

12世紀 ~ 16世紀
武士が台頭した鎌倉時代から室町時代にかけて、アジア諸国の貿易商人たちは大海原をさかんに往来した。京都や博多などの都市をはじめ、各地で商業が発達した。覇権を争った武士たちのあいだでは、禅僧が伝えた水墨画や茶などが富や権力の象徴として流行し、それはやがて日本の伝統文化を代表する茶の湯(茶道)へと発展した。
「4 アジアの海は 日々これ交易」の展示作品
5 丸くなった地球近づく西洋 Smaller World, Closer West

16世紀 ~ 19世紀
室町時代の終わりから安土桃山時代は、ヨーロッパの大航海時代にあたる。アジアに進出してきたヨーロッパ人との交流を通じて、鉄砲やキリスト教が日本にもたらされ、日本からは銀や工芸品などが海を渡った。戦乱が終わり社会が安定した江戸時代、日本は長崎や対馬、琉球、蝦夷地を通じて世界とつながった。日本の磁器や漆器が世界を魅了した一方、国内でも世界への知識は広がり、蘭学など多彩な文化が育まれ、やがて訪れる近代への礎となった。
「5 丸くなった地球 近づく西洋」の展示作品