館長

富田 淳 とみた じゅん:館長
専門:東洋書跡
令和5年10月20日付けで、館長に就任しました。味わい楽しみ、つながり響きあいながら、博物館を介した一期一会を大切にしたいと思います。文化財に潜んでいる「どこでもドア」を見つければ、あらゆる地域、あらゆる時代にご旅行いただけます。あなたも知らない、新しい自分が発見できる九州国立博物館に、ようこそ!
『もっと知りたい中国の美術』(2022年10月30日、富田淳ほか、東京美術発行)
『アジア仏教美術論集 東アジアⅢ 五代・北宋・遼・西夏』(2021年2月28日、富田淳ほか、中央公論美術出版発行)
『別冊太陽 王羲之と顔真卿 二大書聖のかがやき』(2019年2月22日、富田淳ほか、平凡社発行)
『もっと知りたい書聖王羲之の世界』(2013年1月15日、島谷弘幸・富田淳ほか、東京美術発行)
(2)論文
「常盤山文庫の書画コレクション」(2023年8月29日、特集展示《創立80周年 常盤山文庫の名宝》図録『常盤山文庫創立八十周年記念名品選 蒐集のまなざし』、公益財団法人常盤山文庫発行)
「南宋 無準師範墨蹟 禅院牌字「巡堂」」(2023年8月20日、『國華』第1534号、國華社発行)
「憶楊新老師」(2023年3月、紫垣心光:楊新先生追思集、故宮博物院発行)
「王羲之略伝-書聖のまなざし-」、「道真と貫之の曲水宴」、「王羲之から藤原行成へ」、「変革者としての王羲之」(2023年1月31日、東京国立博物館・台東区立書道博物館 連携企画20周年特別展図録『王羲之と蘭亭序』、公益財団法人台東区立芸術文化財団発行)
「宋克の録蘭亭十三跋と銭博の摸宋克蘭亭十三跋」(2023年1月25日、『書法漢学研究第』32号、アートライフ社発行)
「玉筋篆について」(2023年1月17日、究極の篆書表現-玉筋篆・小篆-、謙慎書道会発行)
(3)事業成果/展覧会
● 創立150年記念特集「王羲之と蘭亭序」(2023年1月31日-3月3日、於:東京国立博物館東洋館)
● 特別展「顔真卿-王羲之を超えた名筆-」(2019年1月16日-2月24日、ワーキンググループリーダー、於:東京国立博物館平成館)
● 特別展「台北國立故宮博物院 神品至宝」(2014年6月24日-9月15日、ワーキンググループリーダー、於:東京国立博物館平成館)
● 特別展「書聖王羲之」(2013年1月22日-3月3日、ワーキンググループリーダー、於:東京国立博物館平成館)
● 特別展「北京故宮博物院200選」(2012年1月2日-2月19日、ワーキンググループリーダー、於:東京国立博物館平成館)
副館長

山田信吾 やまだ しんご:副館長/アジア文化交流センター所長
令和3年4月に副館長に就任しました。歴史小説やテレビドラマが大好きですが、「事実は小説より奇なり」と申します。小説やテレビを超えた驚きや楽しさ満載の九州国立博物館。多くの皆様のご来館をお待ちしています。

小泉惠英 こいずみ よしひで:副館長
東京と九州の国立博物館で合計30年以上を過ごし、これまでに日本をはじめ、中国、韓国、インドネシア、ベトナム、タイ、インド、パキスタン、スリランカ、アフガニスタンなどアジア諸地域の展覧会に関わりました。九博では、展示や研究だけでなく、文化財の防災にも取り組んできました。
博物館に展示される作品は、作られた時代を雄弁に物語るもの、愛玩されたもの、破壊や略奪に遭ったもの、篤く信仰されたものなど、ひとつひとつが様々な長い歴史を持っています。そこには、わたしたちがどのような未来を創り出していくかを考えるためのヒントがたくさんあります。
学芸部長

白井克也 しらい かつや:学芸部長
専門:考古学
子供のころお祭りで見た石見神楽がきっかけに神話など叙事詩の世界に触れたためなのか、ギリシャ神話やインドの叙事詩「マハーバーラタ」、ポリネシアの「マウイ神話」などの叙事詩と、造形物や芸能などとの関わりに関する仕事も多く、さまざまな文化現象の背景で“ことば”が大きな役割を果たしてきたことを実感しました。
九博では、金子量重コレクションの影絵人形ワヤン・クリに、インドの「ラーマーヤナ」の主要キャラクターが勢ぞろいしていることを知り、一から楽しく勉強し直しています。
企画課

野尻 忠 のじり ただし:企画課 課長
専門:日本古代史
群馬県出身。東京での学生時代に研究活動をはじめ、奈良での博物館勤務を経て、令和5年4月に九州国立博物館へやってきました。もともとは日本古代の法や制度を研究していましたが、博物館に入ってからは専門分野にこだわらず、奈良を中心に寺社等に伝来する様々な資料の調査に従事してきました。現在は、古写経や聖教(仏教に関わる書物等)を、歴史学の研究素材としてどのように活用できるか、考えを巡らせています。これからも、一つ一つの文化財との出会いを大切に、そのものが持つ情報を最大限引き出し、皆様に正しく魅力を伝えられるよう、研鑽に努めたいと思います。

川畑憲子 かわばた のりこ:企画課 特別展室長
専門:漆工
福岡県福岡市生まれ。専門は漆工史。生まれ育った福岡の地で、博物館職員として働けることに、日々喜びを感じています。
九博では、日本の漆器、中国の漆器、東南アジアの漆器など、さまざまな地域の漆器を展示しています。ぜひお気に入りを見つけて、漆器を好きになっていただけたら嬉しいです。
九州国立博物館トピック展図録『彫漆 - 漆に刻む文様の美』 2011年
●「湖の国の名宝」展出陳漆工品の木地構造について」 『滋賀県立琵琶湖文化館 研究紀要』27号 2011年
●「初音の調度のCT・レントゲン撮影および科学的分析」 徳川美術館秋季特別展「国宝 初音の調度」公開シンポジウムにて招待講演、2010年11月
●「桂春院所蔵「菊唐草文玳瑁螺鈿合子」の木地構造について」 『漆工史』33号 2010年
2012年
●「展覧会紹介 細川家の至宝 - 珠玉の永青文庫コレクション」『文化庁月報』520号(1月号) 文化庁
●「展覧会さんぽ 新春特別公開 徳川美術館所蔵 国宝「初音の調度」」『文部科学時報』2月号 ぎょうせい
2011年
●特別展『細川家の至宝』展覧会図録:執筆 NHK・NHKプロモーション
●特別展『よみがえる国宝』展覧会図録:執筆 九州国立博物館
●特別展『黄檗 - OBAKU』展覧会図録:執筆 九州国立博物館編 西日本新聞社
●トピック展『琉球と袋中上人展 - エイサーの起源をたどる』展覧会図録:執筆 九州国立博物館
●トピック展「日本とタイ - ふたつの国の巧と美」展覧会図録:執筆 九州国立博物館
2010年
●特別展『京都妙心寺』展覧会図録:執筆 九州国立博物館編 西日本新聞社
●トピック展『名品でたどる室町から桃山の茶 茶の湯を楽しむIII』展覧会図録:執筆 九州国立博物館
●トピック展『湖の国の名宝 - 最澄がつないだ近江と太宰府 - 』展覧会図録:執筆 九州国立博物館
●「コレスポンダンス〜私の永青文庫〜」『季刊 永青文庫』72号
2009年
●特別展『工芸のいま 伝統と想像』展覧会図録:執筆 九州国立博物館編 朝日新聞社
●トピック展『新収品 ’05 - ’08 交流する文化のかたち』展覧会図録:執筆
2008年
●特別展『国宝 天神さま』展覧会図録:執筆 九州国立博物館編 西日本新聞社・西日本鉄道株式会社
●特別展「島津の国宝と篤姫の時代」展覧会図録:執筆 九州国立博物館

川村佳男 かわむら よしお:企画課 文化交流展室長
専門:東洋考古
神奈川県鎌倉市生まれ、同県逗子市育ち。湘南ボーイに分類されますが、サーフィン経験なし。史跡と自然に恵まれた環境で遊ぶのが大好きな子供でした。東京の大学と大学院で東洋考古、とくに中国考古を学び、2002年9月から中国の山東大学に留学。2005年7月から東京国立博物館でおもに東洋考古の展示を担当し、2016年4月から九州国立博物館に着任しました。学問に携わるひとりとして、菅公のもとで働かせていただくことは大きな喜びです。仲間たちと力を合わせて智恵を絞り、市民のみなさまと天神様に喜んでいただけるような展示をひとつでも多くかたちにしていきたいです。
●「四川盆地における銅戈の変遷」『東南アジア考古学』第21号、160-188頁、2001年
●「漢代における製塩器交替の背景-土器から金属盆へ-」『地域の多様性と考古学―東南アジアとその周辺』青柳洋治先生退職記念論文集編集委員会 (編集)、雄山閣、173-187頁、2007年
●The Spread of Pottery Miniatures in Han Dynasty China, SCIENTIFIC RESERCH ON HISTORIC ASIAN CERAMICS -PRCEEDINGS OF THE FOURTH FORBES SYMPOSIUM AT THE FREER GALLERY OF ART, 123-132,2008
●「中国三峡地区の塩竈形明器について」『塩の生産と流通』雄山閣、41-76頁、2011年
●‘CULTURE OF HAN AND PRE-HAN DYNASTIES’: Remembering the First Exhibition of Chinese Archaeology in Japan, ORIENTATIONS, vol.44, no.5, 59-61,2013
●「犠尊」『國華』第1418号、37-38頁、2013年
●「東周から漢時代にかけての黒陶着色技法」『中華文明の考古学』飯島武次編、同成社、200-209頁、2014年
●「従上古重器到帝王収蔵,名品倶現」『典蔵 古美術』No.261、2014年
●「考古学による中国塩業史の復元」『東アジアにおける塩業考古学の萌芽研究 科研報告書』2015年
●「秦王朝と兵馬俑の考古学」『秦王朝と兵馬俑 -発掘された歴史の実像-』2015年12月19日、東京国立博物館
著書
●『悠久の美 中国国家博物館名品展』(共著)、東京国立博物館編、2007年
●『誕生!中国文明』(共著)、東京国立博物館他編、2010年
●『北京故宮博物院200選』(共著)、東京国立博物館他編、2012年
●『中国 王朝の至宝』(共著)、東京国立博物館・九州国立博物館他編、2012年
●『東京国立博物館 東洋館 東洋美術をめぐる旅』(共著)、東京国立博物館他編、2013年
●『台北 國立故宮博物院-神品至宝-』(共著)、東京国立博物館・九州国立博物館他編、2014年
●『漢・唐時代の陶俑』(共著)、東京国立博物館編、2015年
●『始皇帝と大兵馬俑』(共著)、東京国立博物館・九州国立博物館他編、2015年
発表
●The Spread of Pottery Miniatures in Han Dynasty China, SCIENTIFIC RESERCH ON HISTORIC ASIAN CERAMICS -PRCEEDINGS OF THE FOURTH FORBES SYMPOSIUM AT THE FREER GALLERY OF ART, THE FREER GALLERY OF ART, Smithsonian Institution, U.S.A, THE FOURTH FORBES SYMPOSIUM, 2008.
●「漢時代における明器の拡散について」成城大学、日本中国考古学会2008年度大会、2008年
●Spread of Lead-Glaze Technique during the Han Dynasty, 北京故宮博物院、2009 International Symposium on Ancient Ceramics, 2009.
●「中国塩業考古学史」青山学院大学、東南アジア考古学会2009年度研究大会、2009年
●「春秋・戦国時代の薄造り青銅器の製作技術」奈良県立橿原考古学研究所、アジア鋳造技術史学会大会、2011年
●「漢代青銅器の工人集団類別-温酒尊を例にして-」駒澤大学、日本中国考古学会2013年度大会、2013年
●「三峡地区的塩竈形明器」中国・山東大学、塩業考古与古代社会国際学術研討会、2014年
●「故宮コレクションと「倣古」-青銅器・玉器のかたちに象徴された伝統」東京国立博物館、特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」記念講演、2014年
●「古代中国における極薄青銅器の製作技法 -東アジア諸地域との比較を視野に入れて-」韓国国立中央博物館学術交流発表会、2014年
●「中国青銅器をめぐる旅 4千年のものがたり」東京国立博物館、東京国立博物館10月月例講演会、2014年
●「漢代青銅容器にみる官営工房の流派」広島大学、日本中国考古学会2014年度大会、2014年
●「古代中国の極薄青銅器にみる製作痕分析-3次元計測、蛍光X線分析を踏まえて-」帝京大学、日本考古学協会平成27年度大会、2015年
●「始皇帝が夢見た「永遠」-兵馬俑と発掘品から読み解く-」東京国立博物館、特別展「始皇帝と大兵馬俑」記念講演会、2015年
●「基調講演 秦王朝と兵馬俑の考古学」東京国立博物館、特別展「始皇帝と大兵馬俑」開催記念国際シンポジウム 秦王朝と兵馬俑 -発掘された歴史の実像―、2015年
担当した展覧会
●特集陳列「古代東アジアの武器」東京国立博物館、2006年9月5日~12月3日
●特別展「悠久の美 中国国家博物館名品展」東京国立博物館、2007年1月2日~2月25日
●特集陳列「漢時代の明器-ミニチュア模型にみる2000年前の暮らし-」東京国立博物館、2007年9月4日〜12月2日
●特集陳列「漢・北朝の俑」東京国立博物館、2008年9月2日〜11月30日
●特集陳列「南太平洋の暮らしと祈り」東京国立博物館、2009年4月7日〜6月7日
●特別展「誕生!中国文明」東京国立博物館、2010年7月6日~9月5日
●特集陳列「南太平洋の暮らしと祈り」東京国立博物館、2011年3月22日〜4月24日
●特別展「北京故宮博物院200選」東京国立博物館、2012年1月2日~2月19日
●特別展「中国 王朝の至宝」東京国立博物館、2012年10月10日~12月24日
●特別展「台北 國立故宮博物院-神品至宝-」東京国立博物館、2014年6月24日~9月15日
●特集「漢・唐時代の陶俑」東京国立博物館、2015年9月1日〜12月23日
●特別展「始皇帝と大兵馬俑」東京国立博物館・九州国立博物館、2015年10月27日〜2016年2月21日・2016年3月15日〜6月12日

西島亜木子 にしじま あきこ:企画課 主任研究員
専門:教育普及
展示をよりおもしろく、わかりやすくするためのワークショップやイベントを企画しています。
また、障がい者や外国人なども楽しめるようにアクセシビリティ向上にも努めています。
現在の趣味は長距離ウォーク。いつの日か太宰府から福岡市内の自宅まで歩いて帰ろうと企んでいるところです。
→太宰府~自宅間20㎞を4時間弱で歩きました。趣味の長距離ウォーク(行橋~別府100キロウォーク)は引退。次の趣味を模索中。

望月規史 もちづき のりふみ:企画課 主任研究員
専門:金工
静岡生まれです。金属工芸分野を担当しています。この分野は、仏具や飾金具、刀剣、甲冑など、その対象領域が非常に幅広いところが魅力です。
九州は、学生時代から登山や島巡りなどでしばしば訪れていました。多くの刺激と活気に満ちあふれたこの博物館で、九州そしてアジアをより深く理解していきたいと思っています。

酒井田千明 さかいだ ちあき:企画課 主任研究員
専門:工芸史(陶磁史)
英国の大学院に留学していた頃、城館や美術館に飾られた華やかな古伊万里の数々を目にしました。日本人として誇りに思うと同時に、もっと探求したいという気持ちが芽生えて、陶磁史の研究の道を選びました。九州は、全国的にも陶磁器の産地が集まる「やきもの大国」です。また、古来より貿易の窓口であったため、大陸から数多くの陶磁器が請来された場所でもあります。その九州の地にある当館で、展示を通じて、陶磁器が物語る文化やその魅力について、多くの方々にお伝えできるようにがんばります。趣味は茶道といけばなの修行です。

桑原有寿子 くわばら ゆずこ:企画課 主任研究員
専門:染織史(日本・東アジア)
大阪府出身、猫好き。染織品、特に平安時代の織物の研究をしています。
衣服やお布団、敷物…。染織品は今も昔も私たち人間にとって一番「身近」な存在ですが、痛みやすかったり、用途を変えて消費したりするため、古いものはなかなか残らず実は謎だらけです。どうも平安時代の人々も、海の向こうの舶来ブランド品がお好みだった様子。当時の外国との窓口であるこの太宰府で、昔のひとが大切にしていた染織品のすばらしさをわかりやすく紹介したいと思います。

小池寧々 こいけねね:企画課 アソシエイトフェロー
専門:仏教絵画史
長野県出身です。宮城県仙台市の大学で学び、長野県須坂市で1年と少し勤務した後、ご縁があり遠く離れた福岡県にまいりました。
大学在学時に、信仰のありようや、その変化を今に伝える美術作品に興味を持ちはじめ、今は中世の仏教絵画を専門に研究しています。海の向こうの異国へのあこがれが強くあらわれた作品をみる機会が多かったため、今も昔も世界に開かれた窓口である九州で、文化財に向き合えることを嬉しく思っています。
作品がもつ様々な情報を、わかりやすく、おもしろくお伝えできるよう精進します。どうぞよろしくお願いします。

奥島正興 おくしままさおき:企画課 アソシエイトフェロー
専門:仏教美術史(仏像)
長崎県佐世保市の出身です。
ちょうど多感な時期に、生まれ育った寺の仏像が文化財に指定され、修理が行われました。
そのとき目にしたのは、像を拠りどころに多くの方々の働きが結びつき、一つの喜びとなっていく光景です。
この忘れられない体験がきっかけで美術史の道に進み、現在は平安時代を中心に、仏像とそれをとりまく人々との関係性によって織りなされた文化や社会について研究しています。
今に伝えられたモノを通して、かつての人々の喜びや祈りを、皆様とそっと分かち合うことができるように、日々の仕事に励んでまいります。

李梅 リ・メイ:企画課 アソシエイトフェロー
シルクロードの町、甘粛蘭州の出身で専門は仏教美術です。
多言語対応アソシエイトフェローとして中国語の部分を担当しています。
日本文化の形成をアジア史的観点から捉えるという九博のコンセプトを大切に、博物館について学習し、それまで積み重ねてきた知識を生かし、的確で理解しやすい表現を求めていきたいと思います。
また、シルクロードと太宰府とをつなぐ架け橋になるよう願っています。

Ryan Sheila Marie ライアン シーラ マリー:企画課 アソシエイトフェロー
アメリカ西海岸のシアトル市出身、長年日本に住んでいる英語教師・和英翻訳者です。
多言語対応アソシエイトフェローとして英語でのコミュニケーションに貢献ができるように努めて参ります。九州での滞在はおよそ20年間ですので、九博を含めてこの地域の良さ、面白さを英語圏の方々に伝えたい気持ちが強くて、九博職員の皆様と一緒に頑張りたいと思っております。

安熙媛 アン・ヒウォン:企画課 アソシエイトフェロー
こんにちは。韓国語担当のアソシエイトフェローとして勤務しております。
韓国からお越しの皆さまが、これまで馴染みのなかったものを少しでも身近に感じられるよう、お手伝いできればと思っております。
文化財に宿る物語を知っていただき、何気なく通り過ぎてしまうかもしれない文化財にも、もう一度目を向けていただけたら嬉しいです。
博物館科学課
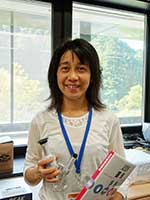
木川りか きがわ りか:博物館科学課 課長
福岡県出身です。理学部生物化学科の博士課程を終えたあと、ご縁があって文化財の生物劣化対策の研究に従事することになりました。独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所で文化財の虫やカビの対策に追われて22年をめまぐるしく過ごし、その間、東京藝術大学大学院のシステム保存学でも授業を担当させていただいておりましたが、このほど故郷九州は福岡の九州国立博物館にて働かせていただくことになりました。「本当に虫が好きですね!」と言われますが、そんなことはありません・・。(多分)どうぞ宜しくお願いします。
●“Microbial deterioration of tsunami-affected paper-based objects: A case study”, Yoshinori Sato, Mutsumi Aoki, Rika Kigawa, International Biodeterioration & Biodegradation, 88, pp.142-149 (2014)
●「津波等で被災した文書等の救済法としてのスクウェルチ・ドライイング法の検討-処理後の塩分残留量について-」、小野寺裕子、古田嶋智子、佐藤嘉則、稲葉政満、木川りか 『保存科学』53 pp.225-231 (2014)
●”Microbial damage of tsunami-affected objects in the Great East Japan Earthquake 2011 and problems with fungicidal fumigation”, Rika Kigawa, Yoshinori Sato, Proceedings of the International Symposium on the Conservation and Restoration of Cultural Property 2012, NRICPT, pp. 35-49 (2014)
2013年
●”Investigation of Acetic Acid Bacteria Isolated from the Kitora Tumulus in Japan and their Involvement in the Deterioration of the Plaster of the Mural Paintings”, Rika Kigawa, Chie Sano, Miyuki Nishijima ,Nozomi Tazato, Tomohiko Kiyuna, Noriko Hayakawa, Wataru Kawanobe, Shigemasa Udagawa, Toru Tateishi, Junta Sugiyama. Studies in Conservation, 58, number 1, pp.30-40. (2013)
●”Addressing the microbiological problems of cultural property and archive documents after earthquake and tsunami”, Ji-Dong Gu, Rika Kigawa, Yoshinori Sato, Yoko Katayama, International Biodeterioration & Biodegradation, 85, pp.345-346 (2013)
●「奈良文化財研究所における被災文書の保管・クリーニング作業場所の微生物環境調査」、高鳥浩介・久米田裕子・佐藤嘉則・木川りか・高妻洋成『保存科学』52 pp.159-166●「津波被災した紙質文化財等から分離した微生物の諸性質」、佐藤嘉則、木川りか、青木睦、赤沼英男、大林賢太郎)文化財保存修復学会第35回大会要旨集(2013)
●「キトラ古墳から分離された微生物の紫外線(UV)耐性試験結果について」、木川りか、喜友名朝彦、立里臨、佐藤嘉則、杉山純多) 『保存科学』52 pp.91-105(2013)
●「非培養法によるキトラ古墳の細菌調査」、佐藤嘉則、木川りか、喜友名朝彦、立里臨、西島美由紀、杉山純多、『保存科学』52 pp.1-10 (2013) 2012年
●「水・塩水で被災した資料の殺菌燻蒸の注意点:資料中の水分・塩分による副生成物の生成量の調査結果について」、木川りか、佐野千絵、佐藤嘉則、犬塚将英、早川典子、古田嶋智子、山梨絵美子、田中淳、森井順之、岡田健、石崎武志 『保存科学』51 pp.121-133(2012)
●「津波等で被災した文書等の救済法としてのスクウェルチ・ドライイング法の検討」、小野寺裕子、佐藤嘉則、谷村博美、佐野千絵、古田嶋智子、林美木子、木川りか 『保存科学』51 pp.135-155(2012)
●「キトラ古墳から分離された細菌や酵母の修復用高分子材料に対する資化性試験」、木川りか、佐野千絵、喜友名朝彦、立里臨、杉山純多、早川典子、川野邊渉 『保存科学』51 pp.157-166 (2012)
●「日光の歴史的建造物における木材害虫・シバンムシ類の効果的な捕獲方法の検討」、木川りか、原田正彦、小峰幸夫、林美木子、川越和四、原田典子、長谷川利行、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』51 pp.173-189 (2012)
●「日光の歴史的建造物で採取した虫糞調査:シバンムシ科甲虫各種間の虫糞形状比較」、小峰幸夫・木川りか・林美木子・原田正彦・三浦定俊・川野邊渉・石﨑武志 『保存科学』51 pp.191-199 (2012)
●「日光の歴史的建造物における捕虫テープに捕獲された甲虫の建物内分布の解析と考察」、林美木子、木川りか、原田正彦、小峰幸夫、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』51 pp.201-209 (2012)
●「ガンマ線および穿孔抵抗を用いた木製柱の内部劣化の診断」、藤井義久、藤原裕子、木川りか、永石憲道、中嶋啓二『保存科学』51 pp.227-233 (2012)
●「霧島神宮の塗装部分から分離された糸状菌の諸性質」、佐藤嘉則、森井順之、木川りか、太田英一、中別府良啓、中山俊介、川野邊渉 『保存科学』51 pp.47-58(2012)
●『文化財の保存環境』第5章“生物被害” 東京文化財研究所編、木川りか、Tom Strang、中央公論美術出版(2012)
2011年
●”Investigation of Effects of Fumigants on Proteinaceous Components of Museum Objects (Muscle, Animal Glue and Silk) in Comparison with Other Non-chemical Pest Eradicating Measures”, Rika Kigawa, Tom Strang, Noriko Hayakawa, Naoto Yoshida, Hiroshi Kimura, Gregory Young. Studies in Conservation, 56, number 3, 191-215. (2011)
●”Conservation of the Mural Paintings of the Takamatsuzuka and Kitora Tumuli in Japan”, Takeshi Ishizaki and Rika Kigawa, Chapter 11 In: Coye, N., eds. Lascaux and Preservation Issues in Subterranean Environments, Proceedings of the symposium held in Paris on February 26-27, 2009. Ed. Maison des Sciences de l'Homme, Paris (France), pp. 261-274. (2011)
●”Efficacy, Effects, Economics: the Problem of Distributing Pest Control Advice to Cover Contingency”, Tom Strang, and Rika Kigawa, In: Integrated Pest Management for Collections, Proceedings of 2011: A Pest Odyssey, 10 Years Later, English Heritage, pp.16-25. (2011)
●”Effects of Fumigants and Non-chemical Treatments on DNA Molecules and Proteins: Case Studies on Natural History Specimens and Protenaceous Components of Museum Objects”, Rika Kigawa and Tom Strang, In: Integrated Pest Management for Collections, Proceedings of 2011: A Pest Odyssey, 10 Years Later, English Heritage, p.115-122. (2011)
●「栃木県日光山内・中宮祠・中禅寺の歴史的建造物を対象とした捕虫テープによる広域虫害調査について」、原田正彦、野村牧人、木川りか、小峰幸夫、林美木子、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』50 pp.101-121(2011)
●「日光の歴史的建造物において捕虫テープ(ハエ取り紙)に捕獲された甲虫の集計方法と調査結果」、林美木子、小峰幸夫、木川りか、原田正彦、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』50 pp.123-132 (2011)
●「日光の歴史的建造物で確認されたシバンムシ類の種類と生態について」、小峰幸夫、林美木子、木川りか、原田正彦、三浦定俊、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』50 pp.133-140 (2011)
●「日光の歴史的建造物を加害するシバンムシ類の殺虫処理方法の検討」、木川りか、小峰幸夫、鳥越俊行、原田正彦、今津節生、本田光子、三浦定俊、川野邊渉、石崎武志 『保存科学』50 pp.141-154 (2011)
●「厳島神社大鳥居の生物劣化調査」、藤井義久、藤原裕子、木川りか、原島誠、喜友名朝彦、杉山純多、早川典子、川野邊渉 『保存科学』50 pp.157-171 (2011)
●「東本願寺阿弥陀堂の生物劣化調査」、藤井義久、藤原裕子、須田達、鈴木佳之、喜友名朝彦、杉山純多、小峰幸夫、木川りか、川野邊渉 『保存科学』50 pp.173-183 (2011)
●「ガンマ線を用いた木製円柱の内部劣化の検出」、藤井義久、藤原裕子、木川りか、川野邊渉、永石憲道、中嶋啓二 『保存科学』50 pp.185-189 (2011) 2010年
●「高松塚古墳修理施設における生物対策について」、木川りか、高鳥浩介、久米田裕子、辻本与志一、川野辺渉、佐野千絵、宇田川滋正、建石徹 『保存科学』49 pp.221-230 (2010)
●「高松塚古墳・キトラ古墳石室内の微生物分離株のアルコール系殺菌剤資化性試験」、木川りか、佐野千絵、喜友名朝彦、立里臨、杉山純多『保存科学』49 pp.231-238(2010)
●「輪王寺の虫害破損について」、原田正彦、木川りか、小峰幸夫、藤井義久、藤原裕子、川野邊渉)『保存科学』49 pp.165-171 (2010)
●「日光山輪王寺本堂におけるオオナガシバンムシの発生状況に関する調査について」、小峰幸夫、、原田正彦、野村牧人、木川りか、山野勝次、藤井義久、藤原裕子、川野邊渉『保存科学』49 pp.173-181(2010)
●「穿孔抵抗測定法を用いた文化財建造物の構造部材の虫害評価に関する一考察 (第2報)-日光輪王寺における虫害を事例として-」、藤井義久、藤原裕子、原田正彦、木川りか、小峰幸夫、川野邊渉)『保存科学』49 pp.183-190 (2010)
●「X線CTによる被害材の調査と虫害の活動検出への応用」、鳥越俊行、木川りか、原田正彦、小峰幸夫、今津節生、本田光子、川野邊渉)『保存科学』49 pp.183-190 (2010)
●「高松塚古墳石室内・取り合い部および養生等で使用された樹脂等材料のカビ抵抗性試験」、木川りか、佐野千絵、高鳥浩介、喜友名朝彦、杉山純多、安部倫子、中右恵理子、坪倉早智子、早川典子、川野辺渉、石崎武志 『保存科学』49 pp.61-72 (2010)
●「文化財公開施設等におけるATPふき取り検査の活用について」、間渕創、木川りか、佐野千絵) 『保存科学』49 pp.1-11 (2010)
●Control of Molds in Museum Environment, eds. and produced by Japan Center for International Cooperation in Conservation, Rika Kigawa, Hajime Mabuchi, Chie Sano. Editorial advisor, Center for Conservation Science and Restoration Techniques, 31 pages. (2010)
2009年
●Combatting Pests of Cultural Property, Tom Strang and Rika Kigawa. CCI Technical Bulletin #29, Canadian Conservation Institute. (2009)
●”The identity of Penicillium sp. 1, a major contaminant of the stone chambers in the Takamatsuzuka and Kitora Tumuli in Japan, is Penicillium paneum 1”, Kwang-Deuk An, Tomohiko Kiyuna, Rika Kigawa, Chie Sano, Sadatoshi Miura, Junta Sugiyama, Antonie van Leeuwenhoek 96 pp.579–592 (2009)
●”Biological Issues in the Conservation of Mural Paintings of Takamatsuzuka and Kitora Tumuli in Japan”, Rika Kigawa, Chie Sano, Takeshi Ishizaki, Sadatoshi Miura, Junta. Sugiyama. In: C. Sano, eds. Study of Environmental Conditions Surrounding Cultural Properties and Their Protective Measures, Proceedings of the 31st International Symposium on the Conservation and Restoration of Cultural Property, held on February 5-7, 2008, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, pp. 43-50. (2009)
●「X線CTスキャナによる虫損部材の調査」、木川りか、鳥越俊行、今津節生、本田光子、原田正彦、小峰幸夫、川野邊渉『保存科学』48 pp.223-231 (2009)
●「日光山輪王寺本堂におけるオオナガシバンムシPriobium cylindricumによる被害事例について」、小峰幸夫、木川りか、原田正彦、藤井義久、藤原裕子、川野邊渉『保存科学』48 pp.207-213 (2009)
●「穿孔抵抗測定法を用いた文化財建造物の構造部材の虫害評価に関する一考察 -日光輪王寺における虫害を事例として-」、藤井義久、藤原裕子、原田正彦、木川りか、小峰幸夫、川野邊渉)『保存科学』48 pp.207-213 (2009)
●「二酸化炭素・酸化エチレン処理がジアゾタイプ複写物に及ぼす影響」、加藤雅人、木川りか、坪倉早智子、中山俊介『保存科学』48 pp.43-50 (2009) 2008年以前
●”Mycobiota of the Takamatsuzuka and Kitora Tumuli in Japan, focusing on the molecular phylogenetic diversity of Fusarium and Trichoderma”, Tomohiko Kiyuna, Kwang-Deuk An, Rika Kigawa, Chie Sano, Sadatoshi Miura, Junta Sugiyama, “Mycoscience“ Vol.49 pp.298-311 (2008)
●「高松塚古墳発掘/石室解体作業に伴う取合部・断熱覆屋使用木材等の防カビ対策:DDACの検討と施工」、木川りか、間渕創、高妻洋成、降幡順子、肥塚隆保) 『保存科学』47、21-26 (2008)
●”Characterization of furunori (aged paste) and preparation of a polysaccharide similar to furunori”, Noriko Hayakawa, Rika Kigawa, Tomoyuki Nishimoto, Kurara Sakamoto, Shigeharu Fukuda, Takayuki Kimishima, Yasuhiro Oka and Wataru Kawanobe, Studies in Conservation, 52, no.3, 221-232. (2007)
●「キトラ古墳のバイオフィルムから分離されたバクテリア・菌類に対するケーソンCG相当品(抗菌剤)の効果」、木川りか、佐野千絵、立里臨、喜友名朝彦、小出知己、杉山純多 『保存科学』46、39-50 (2007)
●「旧日向邸ブルーノ・タウト「熱海の家」の虫害調査-フルホンシバンムシ(Gastrallus sp.)による木材の被害例について-」、木川りか、小峰幸夫、山野勝次、石崎武志 『保存科学』46、131-136 (2007)
●” Levels of IPM Control: Matching Conditions to Performance and Effort”, Tom Strang and Rika Kigawa, Collection Forum, 21(1-2), pp. 96-116. The Society for the Preservation of Natural History Collections.(2006)
●「高松塚古墳の微生物対策の経緯と現状」、木川りか、佐野千絵、石崎武志、三浦定俊 『保存科学』45 pp. 33 -58 (2006)
●「文化財展示収蔵環境におけるIPMプログラム:状況と対策の段階的モデル」、木川りか、Tom Strang 『文化財保存修復学会誌』49, 132-144. (2005)
●『文化財害虫事典』2001年版、2004年改訂版(共著)クバプロ
●「文化財展示収蔵施設におけるカビのコントロールについて」、木川りか、間渕創、佐野千絵 『文化財保存修復学会誌』48 pp.98-113 (2004)
●「博物館・美術館・図書館等におけるIPM:その基本理念および導入手順について」、木川りか、長屋菜津子、園田直子、日高真吾、Tom Strang 『文化財保存修復学会誌』47 pp.76-102 (2003)
●” Effects of Various Fumigants, Thermal Methods and Carbon Dioxide Treatment on DNA Extraction and Amplification: A Case Study on Freeze-Dried Mushroom and Freeze-Dried Muscle Specimens.”,Rika Kigawa, Hideaki Nochide, Hiroshi Kimura, Sadatoshi Miura) Collection Forum 18, No.1-2. pp. 74-85 The Society for the Preservation of Natural History Collections (2003)
●「二酸化炭素殺虫処理における種々の文化財材質の二酸化炭素吸着量」、木川りか、後出秀聡、木村広、宮澤淑子、三浦定俊、Tom Strang『保存科学』42 pp.79-86 (2003)
●「古糊生成過程の生物学的考察 -物性値との関連において-」、木川りか、早川典子、川野辺渉、樋口恒、岡泰央、岡岩太郎『保存科学』41 pp.29-48 (2002)
●「出土木材PEG含浸槽におけるPEG分解菌」、木川りか、横田明、西尾太加二『考古学と自然科学』44 pp.77-88 (2002)
●” Practical Methods of Low Oxygen Atmosphere and Carbon Dioxide Treatments for Eradication of Insect Pests in Japan.” Rika Kigawa, Yoshiko Miyazawa, Katsuji Yamano, Sadatoshi Miura, Hidiaki Nochide, Hiroshi Kimura, and Bunshiro Tomita) Integrated Pest Management for Collections, Proceedings of 2001: Pest Odyssey, pp. 81-88, James and James (2001)
●「低酸素濃度および二酸化炭素による殺虫法 -日本の文化財害虫についての実用的処理条件の策定-」、木川りか、宮澤淑子、山野勝次、三浦定俊、後出秀聡、木村広、富田文四郎)『文化財保存修復学会誌』45 pp.73-86 (2001)

志賀智史 しが さとし:博物館科学課 保存修復室長
専門:日本考古学・保存科学
関西人。九州での生活もだいぶ長くなりました。自宅が太宰府にあるため、休日は太宰府政庁や四王寺山、宝満山付近によく出掛けます。特に四王寺山は気軽に登れる山で、気に入っています。現在の関心事は古代の赤色顔料です。顕微鏡を覗くとホッとしますが、なかなか時間を作れない今日この頃です。
●「赤色顔料」『古墳時代の考古学8 隣接科学と古墳時代研究』 同成社
2011年
●「出土朱の分類の可能性」『日本文化財科学会第28回大会研究発表要旨集』 日本文化財科学会
●「森添遺跡出土の赤色顔料について」『森添遺跡』 三重県度会町教育委員会
2010年
●「高江辻遺跡の赤色顔料について」『高江辻遺跡発掘調査報告書』 筑後市教育委員会
2009年
●「巨大なパイプ状のベンガラ粒子について」『日本文化財科学会 第26回大会研究発表要旨集』日本文化財科学会
●「伝統を継承する先端施設の取り組み - 九州国立博物館の場合 - 」『第33回文化財の保存と修復に関する研究集会』:共同発表 東京文化財研究所
●「奥山古墳の赤色顔料について」『薩摩加世田奥山古墳の研究』 鹿児島大学総合研究博物館
2008年
●「前期古墳に用いられた赤色顔料の一様相」『東風西声 九州国立博物館紀要』第4号 九州国立博物館
●「赤色顔料による先染の織物」『文化財保存修復学会 第30回大会研究発表要旨集』:共同発表 文化財保存修復学会
●「前期前方後円(方)墳から出土するベンガラの地域性に関する研究」『日本文化財科学会第25回大会研究発表要旨集』 日本文化財科学会
●「中島笹塚古墳群出土赤色顔料とその関連資料の微視的・科学的調査」『東谷・中島地区遺跡群9 中島笹塚古墳群・中島笹塚遺跡(1-8区)』 栃木県教育委員会

渡辺祐基 わたなべ ひろき:博物館科学課 主任研究員
専門:博物館科学(木材保存学・応用昆虫学)
愛知県名古屋市出身です。大学にて博士号を取得したのち、九州国立博物館にやってまいりました。学生時代は農学(森林科学)を専攻し、木材を食害する昆虫をテーマとした、ややニッチな研究に取り組んでいました。九博では、X線CTなどの分析機器による文化財の状態・構造の調査や、文化財に被害を与える生物(すなわち虫やカビなど)の対策をはじめとする展示・収蔵環境の管理に携わっています。大学で学んだことを活かしつつも、新たに学ぶことが無数にあります。また、木材などを食べてしまう「シバンムシ」、紙を食べてしまう「シミ」などの文化財害虫をテーマとした、依然としてニッチな研究も続けています。
● 渡辺祐基, 島田 潤, 和泉田絢子, 佐藤嘉則, 木川りか: 残効性ピレスロイド系薬剤の使用によるニュウハクシミ対策の一事例. 保存科学 63, 139–144 (2024)
● Watanabe, H., Shimada, M., Sato, Y., Kigawa, R.: Development and reproduction of a Japanese strain of Ctenolepisma calvum (Ritter, 1910) at room temperature. Insects 14(6), 563 (2023)
● 渡辺祐基: アコースティック・エミッションによる木材害虫の非破壊検出―ケブトヒラタキクイムシの食害を受けた木製民芸品における一事例―. 保存科学 62, 35–42 (2023)
● Watanabe, H., Fujimoto, I., Ito, M., Yanase, Y., Fujii, Y.: Sex identification of adult bamboo powderpost beetles, Dinoderus minutus, based on X-ray computed tomographic observations. Japanese Journal of Environmental Entomology and Zoology 32(4), 171–174 (2021)
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Nondestructive evaluation of oviposition behavior of the bamboo powderpost beetle, Dinoderus minutus, using X-ray computed tomography and acoustic emission. Journal of Wood Science 66, 46 (2020)
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Continuous nondestructive monitoring of larval feeding activity and development of the bamboo powderpost beetle Dinoderus minutus using acoustic emission. Journal of Wood Science 64(2), 138–148 (2018)
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Nondestructive evaluation of egg-to-adult development and feeding behavior of the bamboo powderpost beetle Dinoderus minutus using X-ray computed tomography. Journal of Wood Science 63(5), 506–513 (2017)
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Relationship between the movements of the mouthparts of the bamboo powder-post beetle Dinoderus minutus and the generation of acoustic emission. Journal of Wood Science 62(1), 85–92 (2016)
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Evaluation of larval growth process and bamboo consumption of the bamboo powder-post beetle Dinoderus minutus using X-ray computed tomography. Journal of Wood Science 61(2), 171–177 (2015)
【国際会議】
● Watanabe, H., Kigawa, R., Strang, T.: Seasonal changes in the distribution of head capsule size of a silverfish species. Pest Odyssey 2021- The Next Generation, Online, 20–22 September, 2021
● Watanabe, H., Kigawa, R., Fujiwara, Y., Fujii, Y.: Analysis of larval development and feeding of an Anobiid beetle using X-ray computed tomography. The 51st Scientific Conference of International Research Group on Wood Protection, Online, 10–11 June, 2020, IRG/WP 20-10961
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Nondestructive evaluation of development, feeding, and oviposition of the bamboo powderpost beetle, Dinoderus minutus. The 4th International Conference for Integrated Pest Management for Cultural Heritage, Stockholm, Sweden, 21–23 May, 2019
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Nondestructive analysis of oviposition of the bamboo powderpost beetle Dinoderus minutus using acoustic emission and X-ray CT. The 48th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection, Ghent, Belgium, 4–8 June, 2017, IRG/WP 17-10889
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Nondestructive evaluation of larval development and feeding and pupal ecdysis of the bamboo powderpost beetle, Dinoderus minutus, using X-ray CT and acoustic emission monitoring. The XXV International Congress of Entomology, Orlando, Florida, USA, 25–30 September, 2016
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Evaluation of larval feeding activity of the bamboo powder-post beetle Dinoderus minutus using acoustic emission monitoring. The International Symposium on Wood Science and Technology 2015, Tokyo, Japan, 15–17 March, 2015, 6BP-O11
● Watanabe, H., Yanase, Y., Fujii, Y.: Observation of boring process of larvae of the bamboo powder-post beetle (Dinoderus minutus) using X-ray computer tomography. The 45th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection, St. George, Utah, USA, 11–15 May, 2014, IRG/WP 14-10821
【国内学会(2019年度以降)】
● 渡辺祐基, 川畑憲子, 板谷寿美, 吉川美穂, 田中麻美, 木川りか: 国宝「初音の調度」のうち櫛箱、小角赤手箱、手箱(胡蝶蒔絵)の木地構造および制作技法のX線CT調査. 日本文化財科学会第41回大会, P032, 東京, 2024年7月
● 渡辺祐基: 九州国立博物館におけるX線CTを用いた木質文化財の調査. 2023年樹木年輪研究会・木質文化財研究会合同例会, 仙台, 2023年11月
● 渡辺祐基, 川畑憲子, 板谷寿美, 吉川美穂, 田中麻美, 木川りか: 国宝「初音の調度」のうち机、色紙箱、長文箱(胡蝶蒔絵)の木地構造および制作技法のX線CT調査. 日本文化財科学会第40回記念大会, P024, 天理, 2023年10月
● 渡辺祐基, 木川りか: 文化財害虫の歩行パターン解析手法の検討. 文化財保存修復学会第45回大会, P080, 吹田, 2023年6月
● 渡辺祐基, 川畑憲子, 板谷寿美, 吉川美穂, 田中麻美, 木川りか: 国宝「初音の調度」のうち刀掛、寄り掛り、掛硯箱(胡蝶蒔絵)の木地構造および制作技法のX線CT調査. 日本文化財科学会第39回大会, P-10, 千葉/オンライン, 2022年9月
● 渡辺祐基, 木川りか, 藤原裕子, 藤井義久: X線CTによるオオナガシバンムシの蛹化および羽化の観察. 第72回日本木材学会大会, N15-P-03, オンライン, 2022年3月
● 渡辺祐基, 川畑憲子, 吉川美穂, 田中麻美, 木川りか: 国宝「初音の調度」のうち貝桶、昆布箱、楊枝箱の構造および製作技法のX線CT調査. 日本文化財科学会第38回大会, P-022, オンライン, 2021年9月
● 渡辺祐基, 川畑憲子, 吉川美穂, 木川りか: 国宝「初音の調度」のうち乱箱、長文箱、短冊箱の構造・技法のX線CT調査. 日本文化財科学会第37回大会, P-026, オンライン, 2020年9月
● 渡辺祐基, 木川りか, 藤原裕子, 藤井義久: X線CTによるオオナガシバンムシ幼虫の行動および成長の評価. 第31回日本環境動物昆虫学会年次大会, P-7, 土浦, 2019年11月
【解説、総説等】
● 渡辺祐基: 竹材害虫チビタケナガシンクイの生活史および食害行動の非破壊的手法による解明. 木材学会誌 (印刷中)
● 渡辺祐基: X線イメージングによる木材穿孔性の文化財害虫の検出. 国立民族学博物館調査報告 155, 227–236 (2022)
● 渡辺祐基: X線CTなどによる文化財害虫の検出と診断. 月刊文化財 No.709, 18–22 (2022)
● 渡辺祐基: 九州国立博物館における多種文化財用X線CTスキャナの更新について. 東風西声: 九州国立博物館紀要 16, 228(67) –225(70) (2021)
● 渡辺祐基: 木材穿孔性甲虫類の食害および生態の非破壊評価. 木材工業 73(7), 258–262 (2018)
● 渡辺祐基: (博士論文抄録)竹材におけるチビタケナガシンクイ幼虫の発育および食害行動の非破壊評価. しろあり 170, 42–46 (2018)
● 渡辺祐基: チビタケナガシンクイの食害生態の非破壊評価—幼虫の成長過程と摂食量のX線CTによる評価—. しろあり 164, 43–44 (2015)
【書籍等】
● 渡辺祐基 (分担執筆): 『文化財をしらべる・まもる・いかす―国立文化財機構 保存・修復の最前線―』, 早川泰弘, 髙妻洋成, 建石 徹 編, アグネ技術センター, 東京 (2022)
【受賞歴】
● 「第34回 日本木材学会奨励賞」(2023年1月)
● “Ron Cockcroft Award”, International Research Group on Wood Protection (June, 2020)
● 「第11回 日本木材学会論文賞」(2018年2月)

和泉田絢子 いずみたあやこ:国立文化財機構 文化財防災センター・九州国立博物館 博物館科学課 研究員
専門:保存科学
東京練馬の出身です。文化財の保存環境の管理に従事しており、おもに空気環境の調査に取り組んできましたが、2024年7月より文化財防災に携わることとなりました。
先人たちの手で守り伝えられてきた文化財を、いま目の前で見ることができることに喜びを感じる日々です。博物館資料ならびに地域の文化財の保存に向き合ってまいりたいと思います。
●「博物館の展示収蔵空間における空気環境の管理と対策事例について」和泉田絢子、渡辺祐基、木川りか、『東風西声: 九州国立博物館紀要』18、pp.87-96、2023年
●「循環ファン付き吸着剤(ケミカルフィルター)による展示ケースの空気質改善の試み」和泉田絢子、渡辺祐基、山本花乃、穴井恵理、木川りか、文化財保存修復学会第46回大会、2024年
●「空気汚染物質の放散が少ない材料を用いた展示台の試作と検証」和泉田絢子、渡辺祐基、桑原有寿子、松尾実香、山本花乃、木川りか、文化財保存修復学会第45回大会、2023年
●「展示ケース内VOC濃度低減のための内装材及び換気ファンの効果に関する検証」和泉田絢子、渡辺祐基、桑原有寿子、富松志帆、松尾実香、木川りか、文化財保存修復学会第44回大会、2022年
●「湿度制御した加熱処理による桐箱からの有機酸放散量低減化に関する検討」和泉田絢子、渡辺祐基、富松志帆、松尾実香、木川りか、文化財保存修復学会第43回大会、2021年
●「アクリル絵具の光劣化に関する自然科学的研究」塚田全彦、和泉田絢子、文化財保存修復学会第42回大会、2020年

鴫原由美 しぎはらゆみ:博物館科学課 アソシエイトフェロー
専門:保存修復(油彩画)
宮城県仙台市の出身です。子供の頃から古いものに興味があり、いつしか歴史や美術に関わる仕事を目指すようになりました。九博では文化財の保存修復に関わる業務に携わっています。日本とアジアの様々な文化財に触れ、新鮮でやりがいを感じる毎日です。
文化財の種類によって保存修復の方法や考え方は様々ですが、「後世へ守り伝える」役割があることは間違いありません。少しでも長く、一つでも多くの文化財を未来へ受け継いでいけるように頑張ります。

奥島希子 :博物館科学課 アソシエイトフェロー
専門:保存科学、染織品の予防保存
長崎県出身です。小学生のころに九博がオープンして、たびたび家族に連れてきてもらい、博物館の資料保存について学び始めた大学時代にもよく足を運んでいました。時を経て、そんな場所で働くことができるようになり、とても嬉しく思っています。
私たちが生活しているこの場所で、人びとが時代時代の日々の営みを続けて文化を繋いだ百年、千年という時間をとても尊いものと感じます。来館者のみなさま、また、これからずっと先の未来の人たちにも、博物館資料を通してたくさんのことを感じていただけるよう、日々の時間を丁寧に過ごして、資料保存の研究に努めてまいります。
●「藍染染織品から拡散したインジゴ分解生成物の蛍光特性」奥島希子、塚田全彦、文化財保存修復学会第46回大会、2024年
●「藍染染織品の収蔵時における保存紙の黄変の事例研究」奥島希子、塚田全彦、文化財保存修復学会第46回大会、2024年
文化財課

伊藤信二 いとう しんじ:文化財課 課長
専門:金工史 仏教工芸史
文化庁から九州国立博物館、東京国立博物館、京都国立博物館、東京国立博物館と渡り歩き、当“きゅーはく”は12年ぶりの勤務となります。開館当初の初心と熱意を思い起こすとともに、時代の変革にともなう博物館のあり方をひたむきに考えていきたいと思っています。
福岡は朝倉市杷木の出身。『観世音寺資財帳』にも記述のみえる歴史ある地です。

畑靖紀 はた やすのり:文化財課 主任研究員
専門:絵画(日本・東洋絵画)
昭和46年(1971)生、秋田県横手市出身。開館以来、日々にぎやかな展示室を闊歩する喜びを感じています。ご好意で展示をお許しいただいた作品、ご来館いただいた方々のあたたかい眼差し。皆様の力で、博物館に新たな命を吹き込んでいただいたような思いがして、胸が熱くなります。皆様のご支援に感謝申し上げるとともに、今後とも若い博物館をどうぞよろしくお願いいたします。
●「失われた瀟湘八景図をめぐって」『MUSEUM』第569号 東京国立博物館 2000年12月
●「雪舟年譜」『国華』第1275号 国華社 2002年1月
●「室町時代の南宋院体画に対する認識をめぐって - 足利将軍家の夏珪と梁楷の画巻を中心に - 」『美術史』第156冊 美術史学会 20004年3月
●「雪舟筆四季山水図(石橋美術館別館)再考 - 図様の典拠と制作年代について - 」『仏教芸術』第282号 仏教芸術学会編・毎日新聞社 2005年9月
●「文明十八年の大内氏と雪舟」『雪舟等楊 - 「雪舟への旅」展研究図録』山口県立美術館及び雪舟研究会編・「雪舟への旅」展実行委員会 2006年11月
2016年
●「雪村周継筆龍虎図屏風」「相阿弥筆山水図」『国華』第1443号 国華社 1月
2015年
●「ビオンボ序説 - 大航海時代の日本美術に関する覚書 - 」「メキシコのビオンボ - 副王宮殿図屏風をめぐる諸問題 - 」『東風西声 九州国立博物館紀要』第10号 九州国立博物館 3月
2014年
●「山水画の伝統と雪舟 - 北京と山口で描いた大作 - 」『日本美術全集』第9巻『室町時代 水墨画とやまと絵』小学館 10月
2013年
●「『古画備考』巻二十上「雪舟」について」『原本『古画備考』のネットワーク』 思文閣出版 2月
●「室町水墨画における「写し」 - 図様と表現の観点から」『写しの力 - 創造と継承のマトリクス - 』 思文閣出版 12月
2012年
●「雪舟の心境をめぐる前提 - 人生の節目と選択」『聚美』第2号 青月社 1月
●「雪舟の観音変相図をめぐって」『論集・東洋日本美術史と現場 - 見つめる・守る・伝える』 竹林舎 5月
2011年
●『トピック展示 館蔵水墨画名品展』展覧会カタログ 九州国立博物館 9月
2009年
●「雪舟の中国絵画に対する認識をめぐって」『寧波の美術と海域交流』 東アジア美術文化交流研究会編・中国書店 9月
2008年
●「鏡堂覚円賛白衣観音図」『国華』第1347号 国華社 1月
2007年
●「南蛮屏風小考 - 館蔵品の特色ある主題をめぐって - 」『東風西声 九州国立博物館紀要』第3号 九州国立博物館 10月

森實久美子 もりざね くみこ:文化財課 資料登録室長
専門:仏教絵画史
静岡県出身、香川県育ち。関西にて仏教美術に目覚め、菅公に引かれて太宰府へやってきました。ここ九州は、遠い昔から、多くの人が夢をいだいて海の向こうへと旅立っていった場所です。海を渡った彼らが出会い、驚き、持ち帰った最新の文化や技術が、どのように日本を変えたのか。その片鱗を見つけ、解き明かしたいと思っています。そして、そのことを来館された皆様に伝え、九州の面白さ、奥深さを一層感じていただくこと、それが私の目標です。
●「東大寺における善財童子歴参図の歴史」 『東大寺(別冊太陽)』 2010年
●「高山寺における華厳経絵画の制作について」 『鹿島美術財団年報』26号 2009年
●「華厳海会諸聖衆曼荼羅についての一考察 - 図様の源泉と思想背景を中心に - 」 『国華』1362号 2008年
●「義湘絵についての一考察 - 宋代絵画の受容をめぐって - 」 『フィロカリア』24号 2007年

松浦晃佑 まつうら こうすけ:文化財課 主任研究員
専門:日本近世史
愛知県出身です。京都での大学生活の後、九博に参りました。江戸時代の対外関係やキリシタンを研究テーマにしています。江戸時代のいわゆる「四つの口」のうち、三つは九州にあったため、九州は世界と繋がる重要な地でした。こうした特徴を持っていた九州の博物館で、様々な資料に接することができ、喜びを感じております。私が当館で扱うのは歴史資料です。歴史資料が発する「声」を、是非皆様の目で「聞き」にいらしてください。持てる知識でそのお手伝いをさせて頂きます。

大澤 信 おおさわ しん:文化財課 主任研究員
専門:仏教彫刻史 韓国美術史
埼玉県さいたま市出身。囲碁六段。モットーは「うれしい!たのしい!大好き!」。
九博には私の人生を大きく変えた仏像があります。その仏像は韓国・高麗時代につくられ、やがて対馬に伝わり、近年九博の所蔵品となった「地蔵菩薩遊戯坐像」。学生のときに九博の文化交流展示室で恋に落ちました。この仏像の足跡をたどるように私も計2年間韓国に留学し、3年間対馬で博物館建設に携わり、2018年7月に九博へとやって参りました。この道のりで出会った「韓国」「対馬」「九博」の人と文化財が私の宝物です。
これからも文化財によって結ばれた人とのご縁を大切にしながら、来館者のみなさまが素敵な文化財や人と出会える場を九博でつくっていきたいです。
〈主担当展覧会〉
特別展「最澄と天台宗のすべて」九州国立博物館、2022年2~3月
〈論文・論考〉
2022年
『最澄と天台宗のこころ(別冊太陽 日本のこころ295)』(共著)平凡社
「なぜ対馬の仏像は狙われるのか?」『西日本新聞』8月5日
2021年
「アジアの半跏思惟像と弥勒菩薩」(共著)『奈良・中宮寺の国宝』九州国立博物館編
「九州における最澄と天台宗の軌跡」『最澄と天台宗のすべて』九州国立博物館ほか編
2019年
「対馬・法清寺の諸像にみる「境界」について」肥田路美編『古代寺院の芸術世界(古代文学と隣接諸学6)』竹林舎
2018年
「高麗時代における「被帽地蔵」の図像受容に関する考察」井手誠之輔・朴亨國編『アジア仏教美術論集 東アジアⅥ 朝鮮半島』中央公論美術出版
2017年
「歴史研究が地域で果たすべき役割―国境の島・対馬の実際―」『歴史学研究』第963号
「対馬の島人と仏像の軌跡と現在」九州国立博物館・対馬市編『対馬―遺宝にみる交流の足跡―』
2015年
「高麗時代被帽地蔵菩薩像に関する一考察―対馬伝来・九州国立博物館像の制作年代を中心に―」『美術史』第178冊
〈翻訳〉
2017年
韓国・国立中央博物館編『日韓金銅半跏思惟像―科学的調査に基づく研究報告―』(共訳)
2014年
韓国・国外所在文化財財団編『早稲田大学會津八一記念博物館所蔵韓国文化財』(共訳)

竹内俊貴 たけうち としき:文化財課 専門職
専門:情報システム
滋賀県出身です。これまでは調査に同行して生データを取得したり、そのデータを活用するためのプログラムを組んだり統計分析を行ったりと、文化に関する最初の情報が生成される場で働いていました。
そういった情報が集積される場である博物館は、ひとつひとつの苦労や受け継がれてきた想いが集積する場でもあると考えています。
「情報を扱うこと=関わる人と対話」ということを忘れず、各々が掲げるミッションをより素晴らしいものにするための土台を作り、情報を広く活用する方法を考え・実践していきます。

落合晴彦 おちあい はるひこ:文化財課 資料管理室主任
専門:写真撮影
東京都出身
2015年に写真技師として着任しました。
各国立博物館には文化財専門の撮影する写真技師がおり、作品や資料の調査・研究のため、研究員と共に日々館内スタジオにて撮影を行っております。
展覧会では中々近付けない貴重な作品を、みなさんの目の代わりとなって緻密に再現できるよう試行錯誤の毎日です。写真は図録やポスターのほか、近頃は雑誌や書籍などにも掲載頂くことが多くなりました。ご覧頂ければ幸いです。
総務課

為近雄一郎 ためちか ゆういちろう :総務課 総務課長
令和6年4月に総務課長として着任いたしました。
来館者の皆様方が有意義な体験をすることのできる博物館とすべく、業務を行ってまいります。
よろしくお願いいたします。
渡部珠代 わたべ たまよ:総務課 総務係長
九州国立博物館は、平常展や特別展はもちろんのこと、館内で行われる様々なイベント、四季折々の自然が楽しめる周辺環境など、楽しめる要素がたくさんあると思います。
自分にとっては、好きなものを発見するきっかけをくれる職場です。
ご来場される皆様にとっても居心地の良い場所となれるよう、少しでも貢献したいと思っています。
展示課

齋部麻矢 さいべ まや:展示課 課長
専門:考古学
大阪府生まれ、なぜか本籍は奈良県。小学生の頃に自分の苗字に興味を持ち、中学生の頃は歴史関係の新聞記事を集め、高校生の頃から博物館学芸員に憧れていました。縁あって福岡の地に来ることになり、これまで展示はもちろん、遺跡の発掘調査や文化財の活用事業、広報業務も担当してきました。
歴史の中で伝えられたモノたちには、そこに生きた人々の思いやくらし、そして驚くほどの発想が詰まっていて、ドキドキさせられることばかりです。みなさんにも、たくさんのドキドキを発見していただくお手伝いをしたいと思っています。
九州国立博物館特別展『ポンペイ』2022、九州国立博物館文化交流展特集展示『古代ガラスの世界-岡山市立オリエント美術館蔵品展-』2021、九州国立博物館文化交流展特集展示『しきしまの大和へ-奈良大発掘-』2020
2022年
●「九州国立博物館蔵「豊前國京南郷入覺」銘銅製経筒と入覚妙見社」九州国立博物館紀要『東風西声』18号(共同執筆) 2021年
●「国宝「観世音寺梵鐘調査報告」九州国立博物館紀要『東風西声』16号(共同執筆)
●「筑前国分寺跡の発掘調査成果-調査の概要・主要伽藍について-」『都府楼53号』
2020年
●「古代の役病対策と祭祀~今も昔も~」『都府楼52号』 2018年
●「筑前国分寺出土軒平瓦について一考察」『大宰府の研究』
●「特論 観世音寺と大宰府の古代寺院」『大宰府史跡発掘30年記念特別展展示図録』
●「筑前国分寺の発掘調査『都府楼50号』
2015年
●『発掘された古代国家 展示図録』
2014年
●「西海道の国分寺」『季刊考古学』第129号
2008年以前
●「福岡県の文化財活用の取り組み」『遺跡学研究』第5号 2008
●「九州における初源期の瓦」『古代瓦研究1』2000
●「北部九州の飛鳥・白鳳時代の瓦」『飛鳥・白鳳の瓦と土器』1999
発掘調査報告書
●『ガサメキ古墳群2・3区 皿山古墳群 発掘調査報告書』2014『以来尺遺跡2 発掘調査報告書』2015
●『和井田遺跡 発掘調査報告書』2013
●『西蒲池池淵遺跡Ⅱ 発掘調査報告書』2011
●『西蒲池池淵遺跡Ⅰ 発掘調査報告書』2010
●『下木佐木安堂遺跡・西蒲池池田遺跡 発掘調査報告書』2009
●『向畑古墳群発掘調査報告書』2002
●『船越高原A遺跡 発掘調査報告書』2000
その他
●平成28年熊本地震復興・復旧事業 熊本県派遣 2018

野中まり のなか まり:展示課 主任研究員
福岡県北九州市生まれ。これまで太宰府市を含む近隣市内の中学校で美術を教えてきました。九州国立博物館には、たくさんの作品や資料、体験コーナーがあり、毎回訪れるたびに新たな発見や出会いがありました。これからは、来館する方が感じる「楽しい! わかった! すごい!」の思いを大切にしていきたいです。地域の方をはじめ、多くの皆様にとって親しみやすく、魅力的な博物館となるよう努力してまいります。

岸本 圭 きしもと けい:展示課 主任研究員
専門:日本考古学
大阪府生まれですが、育ちは奈良県の法隆寺の近く。小学生の頃からお寺や古墳をまわっていましたが、考古学をするなら九州だと考えて福岡へまいりました。
古墳時代、特に埴輪を中心に研究してきましたが、高取焼の窯跡の発掘調査を担当してからは近世の陶器にも取り組んでいます。無形文化財にたずさわってからは久留米絣や藍染にも関心をもっています。
文化財がもつ魅力を、より身近に感じてもらえるように工夫していきたいと思います。

小澤佳憲 おざわ よしのり:展示課 主任研究員
専門:考古学
長野県飯田市生まれ。金沢大学で受けた講義で弥生時代・半島との交流に興味をもち、九州大学大学院に進学、それ以来九州で暮らしています。
奉職後、福岡県教育委員会文化財保護課、そして九州歴史資料館で主に遺跡の発掘調査の仕事をしてきました。楽しみにしていた弥生時代遺跡の発掘調査にはなぜかいっこうにめぐり会えない一方で、大野城跡をはじめ古代の遺跡を発掘調査する機会が多く、最近では大宰府を中心とした古代のこと、特に古代山城を主に研究しています。
九州国立博物館では、考古学の楽しさを皆さんと分かち合えるような仕事を手がけられたらと思っています。
論文
2018年
●「豊前市荒堀雨久保遺跡出土木葉文甕の共伴遺物―7世紀後葉頃の土錘・鍛冶関連遺物ほか―」、『九州歴史資料館研究論集』43
●「石垣構築技術から見た鞠智城跡石垣の位置づけ」、『鞠智城と古代社会』第6号
2017年
●「大野城跡出土の鉄製武器」、『九州歴史資料館研究論集』42
2016年
●「豊前市四郎丸窯跡表採資料の紹介―米田鉄也氏コレクション―」、『九州歴史資料館研究論集』41
●「弥生時代成立期前後の集落の一類型」、『考古学は科学か』田中良之先生追悼論文集、同刊行会
●「日韓の古代山城出土軸摺金具」、『季刊考古学』第136号
2014年
●「古代山城出土唐居敷から見た鞠智城跡の位置づけ」、『鞠智城と古代社会』第2号
●「大野城跡第 40 次・46 次・49次調査出土炭化物の年代測定-土塁中出土炭化物の年代-」、『大宰府史跡発掘調査報告書』Ⅷ、九州歴史資料館
●「基肄城跡東北門の唐居敷軸摺穴中に残された軸摺金具について」、『九州考古学』第89 号
2013年
●「弥生時代の集落の変遷と社会」、『新修福岡市史 特別編-自然と遺跡から見た福岡の歴史-』、福岡市
2010年
●「大野城跡第44次・47次調査出土炭化物の年代測定」、『大宰府史跡発掘調査報告書』Ⅵ、九州歴史資料館
●「大野城跡における最近の調査成果」、『古代文化』62巻2号
●「特別史跡大野城跡を襲った平成15年豪雨災害と災害復旧事業について」、『遺跡学研究』第4号
2009年
●「北部九州の弥生時代集落と社会」、『国立歴史民俗博物館研究報告』149
2008年
●「大野城跡第46次調査(北石垣地区)C区城門跡出土の鉄製扉軸受金具の理化学的調査」、『大宰府史跡発掘調査報告書』Ⅴ、九州歴史資料館(大澤正己と共著)
●「古代住居の建替からみた居住集団-筑後川中流域の古代農村集落-」、『九州と東アジアの考古学-九州大学考古学研究室50周年記念論文集-』、九州大学考古学研究室
●「集落と集団1-九州-」、『弥生時代の考古学』8、同成社
2006年
●「刻目突帯文期の集落構成要素」、『日韓交流史理解促進事業調査研究報告書』
●「北部九州の高地性集落-集落動態からの検討-」、『古代文化』58巻2号
2002年
●「弥生時代における地域集団の形成」、『究班』Ⅱ(埋蔵文化財研究会25周年記念論文集)、埋蔵文化財研究会
2001年
●「渡来人をめぐる諸問題」、『弥生時代における九州・韓半島交流史の研究』、九州大学大学院比較社会文化研究院基礎構造講座(田中良之氏と共著)
2000年
●「弥生集落の動態と画期-春日丘陵地域を対象として-」、『古文化談叢』第44集
●「集落動態からみた弥生時代前半期の社会」、『古文化談叢』第45集
学会発表
2018年
●「古代山城石垣構築技術からみた鞠智城跡」、『平成29年度鞠智城跡「特別研究」成果報告会』
2016年
●「古代山城城門出土の軸摺金具」、築城技術と遺物から見た古代山城
●「北部九州古墳時代前期の棒状土錘―大分県臼杵市黒島遺跡出土例を中心に―」、平成28年度九州史学会大会
2014年
●「鞠智城と朝鮮式山城・神籠石-築城技術から見た鞠智城の位置づけ-」、平成25年度鞠智城跡「特別研究」成果報告会
2013年
●「古代山城の考古学的検討」、『第47回古代山城研究会』
2012年
●「朝鮮式山城と神籠石系山城-築城技術の一端からみた分類試案-」、日本考古学協会 2012年度大会
●「豊前地域の集落-古墳時代後期から奈良時代にかけての一考察-(紙上発表)」、第61回埋蔵文化財研究集会
2009年
●「韓日古代山城石積み技術に関する比較研究」、韓国国立文化財研究所学術交流研究発表会
●「日韓古代山城出土の鉄製軸受け金具」、第3回東アジア考古学会・中原文化財研究院研究交流会
●「集落の統合原理」・「単位集団論」、日韓先史時代の集落研究シンポジウム
2007年
●「大野城跡第 45 次調査(北石垣地区)の発掘成果」、第35回古代山城研究会
●「古代住居の建て替え」、平成19年度九州史学会大会
2006年
●「大野城・尾花土塁地区の調査成果」、第33回古代山城研究会
●「玄界灘沿岸域の弥生時代前半器集落の展開」、第55回埋蔵文化財研究集会
●「大野城跡第 45 次調査(北石垣地区)」、第2回東アジア考古学会・(財)中原文化財研究交流学会
2004年
●「弥生時代社会の基礎構成集団」、平成16年度九州史学会大会
1998年
●「玄界灘沿岸地域における中期から後期の集落動態」、第45回埋蔵文化財研究集会
●「集落の動態と画期―福岡県春日丘陵域を対象として―」、平成10年度九州史学会
発掘調査報告書、図録その他
2018年
●『大宰府政庁周辺官衙跡Ⅺ―広丸地区 遺物編―』、九州歴史資料館(共著、主担当)
2017年
●『大宰府政庁周辺官衙跡Ⅹ―広丸地区 遺構編―』、九州歴史資料館(共著、主担当)
●『大宰府政庁周辺官衙跡Ⅸ―大楠地区 総括・遺物図版編』、九州歴史資料館(共著、部分担当)
●『知恩寺跡』福岡県文化財調査報告書第259集、九州歴史資料館(共著、部分担当)
2016年
●『時末遺跡第1・2次、永久笠田遺跡第2次』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告24、九州歴史資料館(共著、主担当)
●『西ノ原遺跡第3・4次、大西遺跡第4次』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告25、九州歴史資料館
●『塔田琵琶田遺跡第4次』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告26、九州歴史資料館(共著、主担当)
●『塔田琵琶田遺跡第6次』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告27、九州歴史資料館(共著、主担当)
●『塔田琵琶田遺跡3・5次、塔田五反田遺跡、塔田キカス遺跡第2次』、福岡県文化財調査報告書第252集、九州歴史資料館(共著、部分担当)
2015年
●「石垣と水門―古代山城の排水施設―」、『特別史跡野城跡(大宰府史跡ガイドブック2)』、九州歴史資料館
●「土塁の築造方法―版築工法の解明―」、『特別史跡大野城跡(大宰府史跡ガイドブック2)』、九州歴史資料館
●『塔田琵琶田遺跡2次』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告22、九州歴史資料館(共著、主担当)
●「弥生時代の環濠集落-北部九州の場合-」、『綾羅木郷遺跡とその時代―環濠集落事始め―』(企画展図録)、下関市立考古博物館
●「大野城の城門」、『四王寺山の 1350 年―大野城から祈りの山へ―』(特別展図録)、九州歴史資料館
2014年
●『石堂大石ヶ丸の氷室ほか』東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告15、九州歴史資料館
2013年(共著、主担当)
●『久路土芝掛遺跡第2次、久路土高松遺跡第2次』福岡県文化財調査報告書第242集、九州歴史資料館
●『彼岸原遺跡2』福岡県文化財調査報告書第241集、九州歴史資料館
2010年
●『特別史跡大野城跡整備事業Ⅴ(下)』福岡県文化財調査報告書第225集、福岡県教育委員会(共著、主担当)
●『福富小畑遺跡D地点』福岡県文化財調査報告書第228集、福岡県教育委員会
2008年
●「北石垣城門と鉄製軸受金具について」、『大野城と四王寺』(トピック展パンフレット)、九州国立博物館
2006年
●『玉田遺跡、船越高原A遺跡Ⅳ、西隈上中川原遺跡』福岡県文化財調査報告書第25集、福岡県教育委員会(共著、主担当)
2005年
●『日詰遺跡Ⅲ』福岡県文化財調査報告書第24集、福岡県教育委員会
2004年
●『堂畑遺跡Ⅲ』福岡県文化財調査報告書第23集、福岡県教育委員会(共著、部分担当)
2003年
●『日詰遺跡Ⅱ』一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第22集、福岡県教育委員会
2002年
●『堂畑遺跡Ⅱ』一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第20集、福岡県教育委員会(共著、部分担当)
2001年
●『大的遺跡Ⅰ・日詰遺跡Ⅰ』一般国道210号浮羽バイパス関係埋蔵文化財調査報告第19集、福岡県教育委員会(共著、部分担当)
2000年
●「九州地方」、『東アジアの囲壁・環濠集落』考古学資料集25、国立歴史民俗博物館

一瀬 智 いちのせ とも:展示課 主任研究員
専門:歴史(日本近世史)
福岡県筑紫野市の出身。乙女座・A型。梅ヶ枝餅大好きです。小さい頃から太宰府天満宮や大宰府政庁跡などはよく訪れて、とても身近な存在だったように思います。
そんな太宰府の地で、好きな歴史や文化財の仕事に携わることを、とても嬉しく思っています。
九博では、古文書や絵図などの歴史資料を担当しています。日本とアジアなど世界との交流の様子や、当時の人々の息づかいを実感させてくれる、とても大切な資料たちです。あまり目立つことがない資料なので、その魅力をお伝えできるよう試行錯誤しながら、皆さんに楽しんでいただける九博をつくっていきたいです。
九州国立博物館特別展『室町将軍―戦乱と美の足利十五代―』(2019)、 九州国立博物館文化交流展特別展『対馬―遺宝に見る交流の足跡―』(2017)、 九州歴史資料館企画展『五卿と志士―維新前夜の太宰府―』(2014)、 九州歴史資料館特別展『長崎街道―世界とつながった道―』(2012)
2019年
●「「嘉禄三年高麗国牒状写断簡及按文」について」九州国立博物館紀要『東風西声』14号(共同執筆)
2018年
●「「朝鮮国告身関係文書」について」九州国立博物館紀要『東風西声』13号
●「太宰府と五卿と明治維新」『太宰府幕末記 五卿と志士のものがたり』大宰天満宮文化研究所
●九州国立博物館特別展図録『京都・醍醐寺 真言密教の宇宙』(分担執筆)
●九州国立博物館特別展図録『王羲之と日本の書』(分担執筆)
2017年
●九州国立博物館特別展図録『タイ~仏の国の輝き~』(分担執筆)
2016年
●九州国立博物館特別展図録『京都高山寺と明恵上人』(分担執筆)
●九州国立博物館トピック展示図録『古伊万里 旧家の暮らしを彩った器』(分担執筆)
●「天草陶石の「紅毛渡」文書とその周辺」、九州国立博物館紀要『東風西声』11号(共同執筆)
●九州国立博物館展示図録『太宰府天満宮の地宝』(分担執筆)
2015年
●九州国立博物館特別展図録『戦国大名―九州の群雄とアジアの波涛―』(分担執筆)
2014年
●九州歴史資料館企画展図録『黒田官兵衛と城』(分担執筆)
●福岡県文化財調査報告書249集『福岡県の中近世城郭1(筑前の部)』福岡県教育委員会(分担執筆)
2013年
●九州歴史資料館特別展図録『戦国武将の誇りと祈り―九州の覇権のゆくえ―』(分担執筆)
2012年
●「伊東尾四郎文書本「筑前国続風土記附録」について」『九州歴史資料館研究論集』37 九州歴史資料館
2009年
●「福岡藩における大宰府跡の保護・顕彰について」『九州歴史資料館研究論集』34 九州歴史資料館
2007年
●「近世中後期における都市の社会構造と祭礼―筑前博多の祇園会と松囃子を事例に―」『九州史学』147 九州史学研究会

秦健太 : はだ けんた:展示課 事務主査
福岡県うきは市生まれ。
教育事務所、九州歴史資料館、県立図書館での勤務を経て九州国立博物館で働かせていただくことになりました。歴史好きなので九博に来られて大変うれしく思います。
研究員の方々と協力して、来館いただいた方にまた来たいと思って貰える博物館を目標に頑張ります。
交流課

中村みお なかむら みお:交流課 課長
令和7年4月に交流課長として着任いたしました。
福岡県久留米市出身、趣味は読書(漫画含む)と美術館・博物館めぐりです。
九州国立博物館には開館当初から足を運び、おこがましくもその魅力を熟知しているつもりでしたが、職員として内側から知るにつれて、予想を超える新たな発見が数多くありました。
開館20周年を迎える記念すべき年にあたり、「誰もが様々な形で、何度でも楽しむことができる九博」の魅力について、これまで以上に広く深く皆さまにお伝えし、今後も末永く楽しんでいただけるように、自らも楽しみながら尽力してまいります。

今井涼子いまい りょうこ:交流課 主任研究員
専門:考古資料
太宰府で生まれ、太宰府で育ちました。学校の遠足といえば、都府楼跡か四王寺山、宝満山。どこか別の土地で生まれ育っていたら、文化財に関わる仕事に就くことはなかったかもしれません。
これまでは福岡県内の遺跡の発掘調査など主に埋蔵文化財を担当してきました。遺跡から出土するものは、人々の暮らしの断片です。そこから読み取れる多くのことを、皆さんにお伝えしたいと思っています。

地脇 技 ちわき たくみ:交流課 主任研究員
令和5年4月より県立高校から転任してまいりました。福岡は古くから大陸や半島との交流の窓口としての歴史を重ねており、多くの文化財や工芸品を持つ地域の一つです。さまざまなイベントやワークショップ等を通して、日本とアジアとの交流や歴史に親しんでいただけるよう努めてまいります。

田中健太 たなかけんた:交流課 主任研究員
令和5年度より小学校から転任しました。
「学校の先生がなんで博物館におると?」とよく聞かれます。
私の役割は九博ボランティアの方と一緒に教育普及活動や交流事業を推進することです。学校の先生や子どもたち,地域の方々にとって九博を身近な場所にしていきたいです。
「山笠のあるけん博多たい!」のように「先生のおるけん九博たい!」と胸を張って言えるよう努めてまいります。

Emily HORST エミリー・ホースト :交流課 国際交流員
令和7年8月に英語圏の国際交流員としてイギリスから着任いたしました。
九州は初めてですが、様々な文化が混ざり合い、自然豊かな九博で働けることを本当に光栄に思っています。これからもその魅力を伝え、更なる国際交流の機会を作りながら、日本の方でも海外の方でもより一層お楽しみいただけるよう尽力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします!

潘 海向 ハン・カイコウ :交流課 国際交流員
大家好!(こんにちは!)令和6年9月に、中国の国際交流員として着任しました。出身は中国の「緑城」と呼ばれる広西チワン族自治区の南寧市です。日本の文化や歴史に触れる機会を大切にしつつ、九博での活動を通じて、両国文化の相互理解、相互交流を深めていければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします!

裵 寭仁 ベ・へイン :交流課 国際交流員
韓国出身。令和6年着任し、交流事業や多言語環境造成に携わっています。
韓国と最も近い九州、その中でも古代日本の交流の窓口であった太宰府で、国際交流員として勤め、うれしく感じます。
今後も海外から来館された方々にさらに心やすい環境を作っていきたいと思います。
広報課

花谷勇一 はなたに ゆういち:広報課 主任主事
令和4年度から九州国立博物館の広報課に勤務し、令和5年度から広報担当となりました。
着任してから新たな発見の連続で、九博は展示も人も環境も魅力がたくさんあっておもしろい場所だと感じています。
そんな魅力を皆様にたくさんお伝えできるよう全力投球で頑張ります!