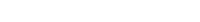【特別展関連コラム】あの日の中国
長江の流れを何にたとえるべきか。きっと春風にゆれる木綿のように、柔らかくゆらりとしたものだろうという私の想像は、2002年、24歳の時に打ち砕かれた。当時、中国語や考古学を勉強するために中国東北部の吉林大学に留学していた私は、重慶市安坪郷という村で発掘調査に参加した折に、長江を眼前にのぞむ機会を得たのだ。初めてみた長江は、雄大というよりはあまりに奔放で荒々しく、一切を呑み込むような凄みがあった。かつて火野葦平が小説『麦と兵隊』でふれたように、長江とは「何かしらその図太さに呆れさせるものがある」存在であった。
長江を眼下に、学生20名ほどで発掘に励んでいたある日。そのうちの数名が、体に赤い発疹ができたと言い出した。そういえば私の首や腕にもポツポツと。これがたまらなく痒い。調べたところ、発疹ができたのはすべて華北(中国北部)出身の学生で、華南出身の学生はみな平気であった。華北は基本的に乾燥地帯。湿潤な南の土地に来て何かが肌にあわなかったのか、それともダニか。 とりあえず、私と華北出身の学生2人、そして重慶のそばの四川出身の学生1人の計4人が、長江を船でくだり、となり町の病院へ行くことになった。四川出身の学生を一人つけたのは、訛りのきつい地元重慶の言葉を標準語に訳してもらうためである。
病院で我々をまっていたのは、細身の老医者だった。黙々と発疹を眺め、触れ、また眺める。この丁寧な診察ぶりに、今まさに発疹の原因が明らかになると、我々の安心と期待は絶頂に達しようとしていた。しかし、診察が終わって、老医者から発せられた言葉に、我々は大いに困惑した。老医者の言葉は、四川省の学生もよく分からないほどに訛りが独特で、何を言っているのかさっぱり分からなかったのである。老医者は、戸惑う我々を気遣うでもなく説明を続け、そして黄色い包みの粉薬をやおら差し出した。そのとき、これまで沈黙を続けてきた黒竜江省出身の学生が苛立つように発した言葉に、私は絶句した。
「先生、結局この薬は塗るんですか? それとも飲めばいいんですか?」
そんな基本的なことさえ聞き取れていなかったのかと、私はもう、驚きを通り越して、なにか悪い夢でもみているかのような錯覚に陥っていった。長江の流域は、考古学的にはさまざまな共通点がみられることは承知していたが、まさか現代において、言葉の壁がこれほどまでに高いとは思ってもみなかった。呆然と病院をあとにした我々の手元には、夢ではないことを証明するかのように黄色い包みの粉薬。我々は、飲むのはさすがに危険と判断し、それからしばらく、本当は飲み薬かもしれない粉薬を、お湯にといては塗る日々が続くのであった。

重慶の発掘現場からのぞむ長江(2002年10月)
筆者 市元塁のプロフィールはこちら