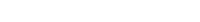鉄炮玉鋳型蒔絵棚(てっぽうたまいがたまきえたな)

【図1】【下】鉄炮玉鋳型蒔絵棚【左】漆塗の地に銀粉を蒔きつけ、金の平蒔絵で文様を描く
わが国に初めて鉄炮が伝えられたのは、一五四三(天文十二)年八月のこと。大隅半島の南方、種子島に一隻の外国船が漂着し、それに乗船していたポルトガル商人が、当時最新鋭の武器(=鉄炮)を携えていたのだ。島の領主種子島時尭(ときたか)は、莫大(ばくだい)な金子(きんす)をもってその鉄炮を買い取り、島に在住していた刀鍛冶清定なる者に複製を造らせた。国産の鉄炮誕生の瞬間である。
その後、この大航海時代の申し子ともいうべき武器は、徐々に九州、畿内、東国へと伝わり、天文年間の終わりから天正初年のころには、近江国の国友、和泉国の堺などで大量生産されるにいたる。当時の鉄炮の有効射程距離は二百メートルほどだったといわれるが、その威力は、従来使用されていた弓矢をはるかに上回るもので、わが国の合戦の様相を一変させるほどの力があった。
一六一五(元和元)年の豊臣家滅亡以降、天下は徳川幕府の支配するところとなり、おおよそ二百五十年におよぶ泰平の世が招来される。しかしながら、その間も鉄炮の重要性は失われることはなく、幕末に洋式銃が移入されるまで、依然として将軍家、諸大名の主要な武器であり続けたのである。
前置きが長くなった。いうまでもないことだが、せっかくの鉄炮も、発射する弾丸がなくては何の役にも立たない。近代の小銃の弾は、先が尖(とが)った円筒形だが、鉄炮、すなわち火縄銃の弾は球形をしている。ここで【図1左】の拡大図をじっくりと見ていただきたい。大きなペンチのように見えるのは、四角い鋳型に把手を取り付けたもの。左右二つに分かれた鋳型には、それぞれ半円形のくぼみが穿(うが)たれていて、そこから小さな孔(あな)が鋳型の外に通じている。玉を作るときには、この鋳型を閉じた状態で、小孔から溶けた鉛を流し込む。それが冷えてから把手を開けば、玉一個の出来上がり、というわけだ。このころの鉄炮の銃身は、一つ一つが手作りなので、口径にばらつきがある。玉もそれに合わせて作る必要があり、この棚のデザインにみられるように、数多くの玉鋳型が用意されていたのだろう。
さて、九州国立博物館が保管することになったこの棚には、もう一つ見どころがある。それは、「蒔絵(まきえ)」である。

【図2】煙管蒔絵提〓笥
玉鋳型棚と同趣のデザインで飾られた作品。画面いっぱいに金の平蒔絵で長煙管の文様を表す
漆を塗った器物の表面に、さらに漆で文様を描き、それが乾かないうちに金や銀などの粉を蒔(ま)きつける。簡単にいえば、蒔絵はそういった装飾法である。この卓抜な技術がわが国に根付いたのは平安時代のこと。その後、鎌倉、室町時代を通じて、さまざまな新機軸が加わり、蒔絵はしだいに成熟の度を深めていく。この棚が製作された江戸時代は、それまでに工夫された多彩な技法がすべて出そろった時期でもあり、まさに蒔絵の黄金期ということができよう。
ちなみに、この鉄炮玉鋳型棚の装飾は、数ある蒔絵技法のなかでももっともシンプルな「平蒔絵」によっている。これは、絵漆で文様を描き、そこに金粉を蒔きつけ、文様の部分だけを磨いて光沢を出す、という方法だが、これでは金粉がしっかりと固着しないため、年を経るうちに文様がかすれてくることがある。数奇者(すきしゃ)のなかには、そのあたりのえもいわれぬ味わいを好む人も多い。
蒔絵で飾った器物は、長く身辺に置いて愛玩するものだけに、そのデザインには、伝統的な花鳥風月をテーマとしたものが多い。ところが、江戸時代に入って、蒔絵がより身近なものになると、従来のおとなしい表現に飽き足りず、より奇抜な趣向が求められるようになる。【図2】に示した煙管のように日常生活で用いる趣味の道具、あるいは玉鋳型のように戦場で用いる剣呑(けんのん)な道具。こういったものを自在にアレンジして、洒落(しゃれ)た文様に仕立ててしまう。先人の、融通無碍(ゆうずうむげ)なデザイン感覚には、まさに端倪(たんげい)すべからざるものがひそんでいるようだ。
キーワード
火縄銃
種子島を通じてわが国にもたらされた銃は、銃身の長さはおよそ1メートル、弾の径は1センチほど。装填するときには、まず、口薬(火薬)を銃口から注入し、さらに弾を杖(さくじょう)とよばれる長い棒で押し込む。その後、火皿の導火薬に火縄を落として発火させる、というやっかいな手順を要する武器であった。慣れた者でも1分に5、6発を発射するのが限界だったといわれている。
案内人 小松大秀(こまつ・たいしゅう)
九州国立博物館学芸部長