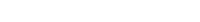展示情報
雪と火炎土器
展示期間:
平成25年1月22日(火)〜3月17日(日)
展示場所:
文化交流展示室 関連第3室
見どころ:
今回のトピック展示の見どころをご紹介します
「なんだ、これは!」。
世界的な芸術家であったかの岡本太郎は、燃え上がるようなエネルギーを込めた縄文土器に出会い、思わず驚きの声を発したと言います。それが、火炎土器(火焔型土器)。川端康成の『雪国』の舞台となった日本有数の豪雪地帯には、今から3000年以上前に静かな日本文化のイメージを打ち壊すような激しい原始美術が花開きました。
巨大地震が紡いだ絆
九博がオープンする前年の2004年、新潟県の中越地域で巨大地震が発生しました。マグニチュード6.8の未曾有の大地震、火炎土器のふるさとであった津南町も震度5強の揺れによって、多くの火炎土器が被災しました。余震が続き、いつ揺れがまた襲ってくるとも分りません。そんな時、約1000km以上離れた九州の太宰府の地に、火炎土器たちは修理のために避難してきたのです。それが縁で、九博では火炎土器を展示しており、今回のトピック展示の開催となりました。
魅惑的な原始のデザイン
火炎土器の魅力はその形もさることながら、渦文や三角形が迫ってくる圧倒的なボリューム感です。今回の展示では、1点1点の火炎土器を立ち止まってじっくりと味わっていただきたいと思います。さらに、いくつかの土器はガラス越しでなく、露出でご覧いただけます。また、迫力ある写真でも紹介いたします。3000年以上前の人々が創造した美の世界へとご案内いたします。
雪国のくらしと風土
津南町は日本有数の豪雪地帯として良く知られています。4m〜5mの積雪量もめずらしくありません。そんな雪国には独特の文化が育まれています。九州ではなかなか感じ取ることの出来ない雪国の風土が生んださまざまな文化財をご紹介します。
触れる火炎土器
今回のトピック展示では、実物の火炎土器に触れることができます。火炎の形をなぞったり破片に直に触れて、縄文時代の人々のぬくもりを感じ取ってみて下さい。
トピック展示「雪と火炎土器」開催までの道のり
展覧会ができるまでを、九博ブログでご紹介します。
ご期待下さい。
【九博ブログはこちら】
|
マジカルな文様が彫刻された石棒 |
|

|
彫刻石棒 石棒というのは、男性のシンボルを象ったまじないの道具とされています。そこに、「S」字を組み合わせたようなまじないの文様が・・・。いかにも縄文らしいマジカルパワーにあふれた造形を展示室でご覧下さい。 |
|
かわいらしい顔をした土偶 |
|
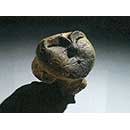
|
土偶 可愛らしい顔をした、おちょぼ口の土偶。子供の顔でしょうか?くっきりとした眉毛は笑っているのか泣いているのか。声が聞こえてきそうな土偶です。 |
シンポジウム「雪と火炎土器」
縄文土器を代表する火炎土器は、口縁の波状文様が燃えさかる火炎を思わせることからそう名付けられました。新潟県の信濃川流域を中心とした狭い範囲に分布する火炎土器の魅力に迫ります。
13時00分〜17時00分



シンポジウム「雪と火炎土器」事務局(「西広」内)
FAX:092-717-1685
e-mail:kyuhaku@nishiko.co.jp
お問い合わせ:電話092-717-1685(平日10:00〜18:00 *12:00〜13:00を除く)
写真展「津南 冬の生活と景色」
津南町のある中越地方は、世界的な豪雪地帯です。津南在住の写真家たちが撮影した津南の冬の風景と人々の生活をご覧ください。
ハンズオン体験「ホンモノの火炎土器に触れてみよう」
展示室内で、ホンモノの火炎土器の破片を手に取ることができます。5000年前の縄文人がつくった土器の重さや肌触り、造形をぜひその手に感じてみてください。
1月27日(日)
2月3日(日)・10日(日)・11日(月・祝)・17日(日)・24日(日)
3月3日(日)・10日(日)・17日(日)
各14:00〜16:00
(九州国立博物館4階文化交流展示室関連第3室)
*参加は無料ですが、文化交流展の観覧料が必要となります。
体験ワークショップ「アンギンの編み方をつかったコースターづくり」
火炎土器のふるさと津南町には、「アンギン」と呼ばれる独特の技法でつくった布があります。この「アンギン」の基本的な編み方を使ってコースターをつくります。
各13:30〜15:30
2月15日申し込み締切り(申し込み期間内でも定員になり次第締め切らせていただきます)。
「雪と火炎土器」体験ワークショップ事務局(「西広」内)
FAX:092-717-1685
e-mail:kyuhaku@nishiko.co.jp
お問い合わせ:電話092-717-1685(平日10:00〜18:00 *12:00〜13:00を除く)