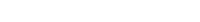過去の展示情報
よみがえる弥生都市

展示期間:
平成20年8月20日(水)〜11月16日(日)
展示場所:
文化交流展示室第3室
概要:
「魏志倭人伝」に登場する「一支国」の王都と目される「国指定特別史跡 原の辻遺跡」と九州最大級の弥生時代の環濠集落「国指定特別史跡 吉野ヶ里遺跡」、そして多重環濠を有する水に浮かぶ弥生集落「国指定史跡 平塚川添遺跡」。弥生時代を代表する北部九州の三遺跡が「九州北部三県姉妹遺跡」を締結して10周年を迎えることを記念して各史跡の特徴、地域性及び共通性等を踏まえ、各史跡から出土した資料を展示します。
今回のトピック展示における三遺跡は「弥生時代の大規模環濠集落」という共通性を持ち、それぞれが地域における拠点集落として機能していました。「原の辻遺跡」は「一支国」の中心として、そして「吉野ヶ里遺跡」「平塚川添遺跡」は明確にはされていないものの弥生時代の「クニ」の中心集落であったことは疑いえません。未だ謎のままである「邪馬台国」を解明する鍵が秘められた各遺跡からの出土品を関連資料を交えて展示します。

|
人面石 1点 厚みのある凝灰岩の自然石を利用して製作されたもので長さ10.2cmの楕円形をしています。目と口は円坑で表現し、鼻は削り出しで浮き彫り、目の上には眉を二条の弧で表現して人の顔を形どっています。用途については明確ではありませんが、何らかの祭祀儀礼に用いられたものと考えられています。 |

|
銅鐸 1点 吉野ヶ里遺跡の中心からは離れた谷部で埋納されていた九州初出土となる銅鐸。これまで鋳型や小銅鐸、鐸形土製品は出土していましたが、銅鐸そのものは発見されていませんでした。この銅鐸は横帯文を特徴とし、中国地域で4例が知られている「福田型」と呼ばれる型式のもので、島根県木幡家銅鐸が同笵であることが判明しています。 |