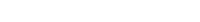イベント
古代の東アジアでは、中国を中心とした外交や交易が展開される中で、律令や仏教・儒教などを共通要素とする「漢字文化圏」が形成されていきました。日本をはじめとした周辺諸国では、漢字文化の受容を下地としながら、政治制度としての律令を受け入れ、律令国家の建設を目指しました。
その大きな歴史の流れは、後の時代になって編纂された『日本書紀』をはじめとした歴史書などから知ることができますが、いきいきとした古代史像を描き出すためには、木の札に文字を書いた「木簡」をはじめとした出土文字資料の存在が極めて重要です。
今回のシンポジウムでは、近年出土例が増え注目度が高い韓国の木簡と日本の木簡との比較を中心として、日韓両国における漢字文化のひろがりと木簡を利用した文書行政の実態に迫ります。
| 日時 |
平成18年9月17日(日)10:00〜17:00 |
| 場所 |
九州国立博物館 1階 ミュージアムホール |
| プログラム |
日韓の研究者(日本3名、韓国2名)による古代木簡に関する講演、研究報告および討論 |
| 9:30 |
開場 |
| 10:00〜11:00 |
講演「漢字文化のひろがり」 平川 南氏(国立歴史民俗博物館長) |
| 11:10〜11:50 |
報告「日本における漢語・漢文の受容と和文表記」 吉村武彦氏(明治大学文学部長) |
| 11:50〜13:10 |
【昼食・休憩】 |
| 13:10〜13:50 |
報告「木簡の世紀以前 - 律令制の成立と日本の木簡 - 」 渡辺晃宏氏(奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部史料調査室長) |
| 13:50〜14:30 |
報告「韓国における木簡出土遺跡」 鄭 桂玉氏(大韓民国文化財庁発掘調査課学芸研究官) |
| 14:30〜15:10 |
報告「韓国出土の木簡」(仮題) 李 鎔賢氏(大韓民国国立中央博物館考古部学芸研究士) |
| 15:20〜15:30 |
【休憩】 |
| 15:30〜17:00 |
討論 |
申込者本人の〔1〕郵便番号〔2〕住所〔3〕氏名(ふりがな)〔4〕電話番号等を明記の上、ハガキで申し込んで下さい。先着順で100名に入場整理券を郵送します。定員になり次第締め切ります。
※ いただいた個人情報は厳重に管理し、本シンポジウムに関する連絡以外の用途には使用いたしません
【申し込み先】
〒818−0118
福岡県太宰府市石坂4−7−2
九州国立博物館イベント事務局「木簡シンポジウム」係 宛