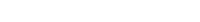博物館からのお知らせ
|
|
そろそろ梅の花が香る季節ですね。春はもうそこまで来ています。 かわいいお雛さまが九博の1階エントランスに登場します。 雛祭りの時期だけの限定展示、観覧は無料です。 九博で愛らしいお雛さまと春を迎えませんか。 |

| ○ |
期日 平成20年1月22日(火)〜3月9日(日) |
| ○ |
場所 お雛さま:九州国立博物館1階エントランス |
| ○ |
観覧料 無料 |
| ○ |
お雛さまについて ・作者、原米洲について 雛人形は東京浅草に工房をかまえていた人形師、原米洲(はらべいしゅう)氏(1893-1989)の作品です。明治26(1893)年栃木県宇都宮市に生まれ、昭和41(1966)年には人形を仕上げる際に使う米洲氏独自の技法、「胡粉仕上げ(ごふんしあげ)」が無形文化財に指定されました。 米洲の作品には皇室に献上された御所人形(ごしょにんぎょう)もあり、国内を始めパリやスウェーデンの美術館にも展示されています。この作品は、個人の方から御寄贈いただいたものです。 ・人形の特徴 木目込み(きめこみ)人形と呼ばれる形式を用いています。「木目込み」とは木彫りの人形に金襴(きんらん)などの切れ地をはり、その端を彫った溝に埋め込んで衣装とした人形で、江戸中期ごろから作られています。 雛人形には米洲独特の技法である「胡粉(ごふん)仕上げ」「笹目(ささめ)」が施され、優しさの伝わってくる表情をしています。衣装は桃山時代の衣装をもとに作られ、塗りも江戸時代以来の伝統的な技法をもちいています。お顔の表情が特徴的で、米洲得意のかわいらしい童顔です。  胡粉仕上げ 胡粉は牡蛎(かき)の殻を粉にしたもの。粒子の粗い胡粉を沈殿させ、さらさらになった上澄みだけを使って数十回の重ね塗りをして人形の肌を仕上げます。胡粉は温度や湿度に敏感に反応し、季節によってはせっかく塗ったものがひび割れることもありました。それをどんなときにもひび割れることなく、美しく仕上げるための独自の技術を米洲が確立したのです。 笹目 これも米洲が考案した面相の技法。米洲人形の目や眉は、一筆描きではなく、笹の葉の葉脈のような数十本ものごく細い線で描き入れられています。墨の色だけでも数種にも及ぶこの手間と高い技術が、繊細で優美な人形の表情を創りだしています。 |